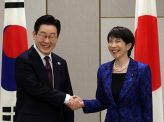「5キロ2000円」の衝撃:コメ政策転換の序章か?

宮家邦彦(立命館大学 客員教授・外交政策研究所代表)
宮家邦彦の外交・安保カレンダー 2025#21
2025年5月26日-6月1日
【まとめ】
・農水大臣がコメの値段を5キロ2000円台にすると表明し国内で騒ぎに。
・アメリカでコメの値段を調べた。品種や量、店舗で価格が大きく異なる。
・日本のコメ政策の抜本的な転換と既得権益打破が重要だ。
今週は、久々の休暇も兼ねて、米国に来ている。日本出国の二日前、新たに任命された農水大臣が「コメの値段を5キロ当たり2000円台にする」などと表明したものだから、日本国内は大騒ぎになった。という訳で、今週は「外交安保」ではなく、コメの値段の話から始めよう。
米国入国後、農水大臣の発言が「5キロで2000円台」から「5キロで2000円」に変わった、というニュースを聞いて更に驚いた。それなら米国でカリフォルニア米は小売価格でいくらなのかなぁ。俄然興味が湧いてきたので、早速調べてみた。勿論米国といっても広いし、小売価格は、品種や量、購入店舗によって大きく異なる。
米本土で、カルローズ米(Calrose Rice)は概ね5キロ(約11ポンド)当たり20ドル~30ドル(3,000円~4,500円)程度のようだ。でも、値段の安いWalmartではカルローズ米が5キロ当たり6.58ドルから、Amazonでは5ポンド(約2.27キロ)が6ドル程度から、20ポンド(約9キロ)も37ドルぐらいで販売されているらしい。
一方、銘柄米ではカリフォルニア産コシヒカリが 2キロで21.47ドル、同じくカリフォルニア産の玉錦が 2キロで15.99ドルという報告もあるそうだ。ちなみに、ハワイのドン・キホーテでは、カルローズ米が50ポンド(22.7キロ)で44.99ドル、日本産コシヒカリのブレンド米が5キロ24.99ドルで売られていた。よくわからん!
要するにコメが安いと言われる米国でも、その値段は千差万別だということ。それにしても新農水大臣は随分思い切った決断をしたものだと思う。日本の一部には、「減反を廃止して増産し、剰余分を輸出に回すべきだ」と主張する向きもあるが、実はそれって、日本の農業政策に抜本的な転換を迫るものだ。
備蓄米の随意契約が一般化すれば、俗に言われる「農協・コメ議員・農水省」という「鉄のトライアングル」に風穴が開く可能性が生まれ得る。コメ政策改革派は、食料安全保障の強化、国際競争力の向上、農家の所得向上、消費者利益の追求、既得権益の打破が必要だと主張するが、新農水大臣はそこまで考えているのだろうか。
本気で「既得権の打破」を追求すれば、減反政策による「高米価・補金」システムを維持しようとする林水産省、JA農協、コメ議員が必死で反撃してくるだろう。「5キロ2000円」政策は、単なる大衆迎合策か、それとも本格的なコメ政策の転換への序曲となるのか、が大いに気になる。
筆者は農業の専門家ではないが、コメ減反政策そのものを改革しようとすれば、それはコメ議員だけでなく、自民党議員の多くの政治生命を左右し、「鉄のトライアングル」だけでなく、戦後の保守政治のあり方そのものが問われる事態にすらなりかねない。この点は今週のJapanTimesに書くつもりなので、ご一読願いたい。
もう一点、今週気になったことがある。やや旧聞に属するが、先週18日に新ローマ教皇レオ14世の就任式がヴァチカンのサンピエトロ広場で開かれ、日本からは麻生元首相が特派大使として参列した。しかし、考えてみれば、新教皇は米国シカゴ生まれ。今回米国に来て、改めてその意味の大きさを痛感している。
そもそも何故米国出身の枢機卿が教皇に選ばれたのだろうか。これまでは米国から教皇は選ばれない、という都市伝説すらあったそうだ。その理由は、「既に超大国である米国に更なる力を与えかねない」からだという。しかし本当にそうなのか。考えてみたら、それは無理筋、やはり「都市伝説」でしかなかったのかもしれない。
そもそも米国でカトリックは少数派である。国家の成り立ちそのものが「反カトリック」的だったし、「ウェストサイド物語」にも描かれた通り、カトリックは差別と偏見の対象でさえあった。そのカトリックのトップに(ペルー在住が長かったとはいえ)アメリカ人が就いたことは、米国、特に米国内政にとって如何なる意味があるのだろうか。
カトリック教会内では「妊娠中絶」と「同性愛」について議論が続いている。これらはいずれも米国内では選挙イシューとなるほど社会を分断する大問題だ。また、カトリック教会には、教義上の理由から、離婚、移民、気候変動、軍縮について決して妥協できない諸原則もある。
その意味では米国出身の新教皇は、米国出身だからこそ、ワシントンとの関係が微妙であり、慎重の上にも慎重を期す必要があるだろう。では、なぜ枢機卿団は米国出身の枢機卿を教皇に選んだのか。米国人である「にも拘わらず」選ばれたのか、逆に、トランプ政権を牽制するため、即ち、米国人「だからこそ」選ばれたのか。
いやいや、いずれも「深読みし過ぎ」で、実はどちらでもないのか。この点は来週、更に掘り下げて分析し、産経新聞のWorldWatchにも書こうと思う。
最後にガザ・中東情勢について一言。26日にイラン外務省報道官は「米国との核合意を確保するためにウラン濃縮を一時的に停止することは検討しない」「ワシントンとの第6回協議の日程はまだ決まっていない」などと述べたらしい。
イランが合意のため濃縮を「3年間凍結する」可能性があるとの報道についても、同道官は「イランはそんなことは決して受け入れない」と述べ、米国との暫定合意の可能性を否定したという。うーん、でも、真実だとしても、そんなこと、記者会見で言える訳がないだろう。今のイランは、米国以上に、「合意」を必要としている筈なのだから・・・。今週は移動が続くので、このくらいにしておこう。いつものとおり、この続きは今週のキヤノングローバル戦略研究所のウェブサイトに掲載する。
トップ写真:コメを買う女性(イメージ)出典:Kanawa_Studio/GettyImages
あわせて読みたい
この記事を書いた人
宮家邦彦立命館大学 客員教授/外交政策研究所代表
1978年東大法卒、外務省入省。カイロ、バグダッド、ワシントン、北京にて大使館勤務。本省では、外務大臣秘書官、中東第二課長、中東第一課長、日米安保条約課長、中東局参事官などを歴任。
2005年退職。株式会社エー、オー、アイ代表取締役社長に就任。同時にAOI外交政策研究所(現・株式会社外交政策研究所)を設立。
2006年立命館大学客員教授。
2006-2007年安倍内閣「公邸連絡調整官」として首相夫人を補佐。
2009年4月よりキヤノングローバル戦略研究所研究主幹(外交安保)
言語:英語、中国語、アラビア語。
特技:サックス、ベースギター。
趣味:バンド活動。
各種メディアで評論活動。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧