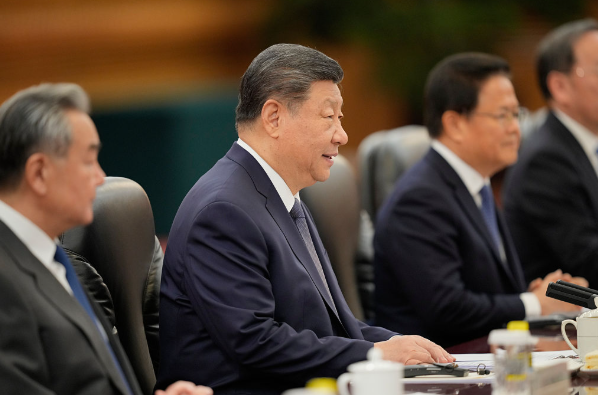スマホ依存の危険とは

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)
「古森義久の内外透視」
【まとめ】
・アメリカで「不安な世代」本が出版され、ベストセラーに。
・スマホは、肉体的・知的活動、家族や友人との接触などが減少、少年少女の成長を妨げていると警告。
・スマホはいまや人間の活動に欠かせない道具ではあっても、その奴隷になってはならない
「スマートフォンへの依存は人間の成長に障害を起こし、とくに若い世代の精神発達を阻害して、多様な症状を起こす危険がある」――アメリカでこんな内容の本が話題を広げている。スマホへの世代を問わない依存ではアメリカよりむしろ度合いが高いようにみえる日本でも、注意を払うべき警告だといえよう。
その問題の書はアメリカで3月末に出版された「不安な世代(The Anxious Generation)」と題する本だった。副題は「子供時代の大規模な再配線がいかに精神障害の伝染を引き起こしているか(How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness)」とされていた。「再配線」とは人間のコミュニケーション(交信)の経路がスマホにより根本から変わり、その経路である「配線」が変化したことを意味するのだという。著者はニューヨーク大学の著名な社会心理学者のジョナサン・ハイト教授である。この書は発売直後にニューヨーク・タイムズの全米ベストセラーで1位となった。アメリカの主要メディアはつぎつぎにその内容や売れ行きを詳しく報じ、話題の輪が全米に広がったというわけだ。
同書の主旨は、スマホの普及で人間本来の肉体的・知的活動、家族や友人との接触、自然の観賞などが消失寸前まで減少し、とくに10代の少年少女の正常な成長を妨げている―-という警告だった。ハイト教授は背景として以下の諸点を報告していた。
▽2016年以降の調査ではアメリカの10代の男女の79%、8歳から12歳までの子供の28%がスマホ類を持つという結果が出た。10代の男女は1日に平均7時間をスマホ使用に費やすという。
▽2010年から2024年の間に、アメリカをはじめとする西側諸国では10代の鬱病症状が男性で165%、女性で143%と、大幅に増加した。この増加は少年少女たちがスマホ類への没頭により内向性が過剰となり、さらに頭脳の成長が阻害されたためとみられる。
▽性に関する知識や体験も肉体的に適切ではない10代の早い時期から男女ともにスマホ経由で早められる。その結果、社会の規範に反する行動につながる例が多い。
ハイト教授は以上のような背景を基礎として、その結果、いまの成長期の若い男女に起きている現象について多角的に以下の報告を伝えていた。
▽人間の頭脳は思春期に最大の成長、最大の再編成を迎えるが、その成長への発展を自然に促進する動きがスマホへの没頭で妨げられて、頭脳内に構造的な変化を起こすことになる。
▽少年少女たちはスマホへの没入により自然な成長の過程で突然に、同世代の男女と遊ぶ、話す、遊ぶという行動を激減させてしまう。
▽人間の健全な成長、発展には具体的な社会活動が欠かせないが、スマホへの没頭は少年少女からその機会を奪ってしまう。その結果、少年少女の多くが現実の世界を認知しないところまでいってしまう。
以上の指摘も考えてみれば、ごく当然のように思えてくる。スマホの登場する文字もイメージもすべて仮想世界である。現実世界ではない。人間が成長するには現実世界との接触が不可欠なことは自明だといえる。その成長期の真っ最中にある若い人間が現実の世界には接することなく、仮想の世界に没入し続ければ、その成長が歪んでくることは当然だろう。
アメリカの主要メディアのなかではまず大手紙のウォールストリート・ジャーナルがこの書での警告で大きく取りあげた。同紙の看板コラムニストのペギー・ヌーナン記者が4月上旬、「私たちは子供をスマホから救えるか」という見出しの長文記事で同書の内容を紹介した。スマホの広がりの現状は若い世代の成長に重大な危機を生んでいる、ハイト教授の警告を詳しく伝えたのである。
ではどうすればよいのか。当面なにをすれば、10代の男女の成長のゆがみを減らすことができるのか。
ハイト教授はまず当面の是正策として、高校生未満のスマホの全面禁止、高校でも教育時間内のスマホの所持禁止、16歳以下のソーシャルメディアの禁止などを提案していた。
この是正策が実際にどこまで実行されるのかは疑問だが、この種のスマホ追放策が権威のある学者から打ち出されるようになったアメリカのスマホ事情は日本側でも知っておくべきだろう。なぜなら、スマホへの没入という点では、アメリカよりも日本の方がその度合いがずっと高いように思えるからだ。たとえば、ワシントンと東京の地下鉄では乗客のスマホ使用の程度が明らかに違う。東京では座っている乗客のほぼ全員がスマホをしっかりと握り、操作に没入している。ワシントンの比率は約半数といえそうだ。
東京では地下鉄に限らず、他の乗り物の内部でも駅でも街路でもスマホを握り、見つめたままの男女に満ちている。カフェでも母と娘がまったく言葉を交わさずに、それぞれ自分のスマホに没入している。報道の世界でさえも、日本のテレビでの火災や豪雨の現場報告で、現状を指し示すはずの記者が単に自分のスマホの文字を読み上げる、という光景が目立つ。スマホはいまや人間の活動に欠かせない道具ではあっても、その奴隷になってはならない、とさえ感じてしまう。

▲図 The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness 出典:amazon
トップ写真:スマホを見て地下鉄に乗るアジア人 出典:iStock / Getty Images Plus
あわせて読みたい
この記事を書いた人
古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授
産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧