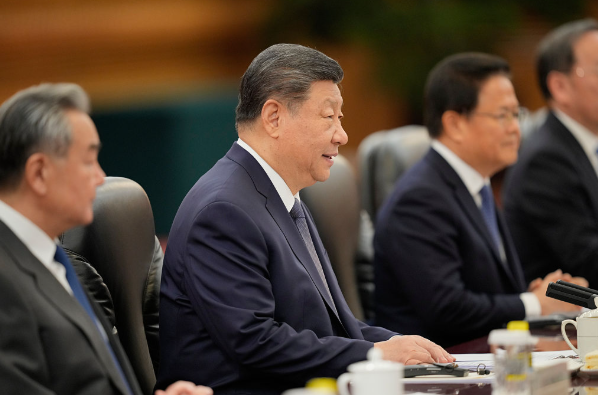ベトナム戦争からの半世紀 その41 日本人記者の進退は

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)
【まとめ】
・1975年4月、北ベトナム軍の大攻勢が迫るサイゴンで、日本人記者の生命の安全確保が課題に。
・日本政府は日本人退避のため日本航空の特別救援機を計画したが、米軍ヘリでの外国人ジャーナリスト避難計画も存在した。
・最終的に、各報道機関はサイゴン常駐特派員1人を米軍ヘリで脱出させる決定を行った。
北ベトナム軍の大攻勢が迫るサイゴンでは私たち日本人記者がその危機にどう対処するかが現実の課題となった。つまり自分たちの生命の安全である。この課題は当然ながら記者だけに留まらず、南ベトナムにいる外国人全体にも差し迫っていた。
北軍が首都圏の入口にあたるスアンロクを制圧した1975年4月20日ごろからサイゴンの外国人社会では危機意識が高まった。翌日のチュー大統領辞任はさらにその危機感を強めた。在留外国人の間でもとくに職業上の責任や任務のない家族などは国外への撤退を始めていた。
その一方、それまで乗客の多かった諸外国の民間航空会社もサイゴンへの運航を停止するようになった。旅客機の運航自体への危機を考えざるをえない状況となったのだ。
4月21日には香港のキャセイ航空がサイゴンへの運航を止め、サイゴン支店をも閉鎖した。24日にはタイ国際航空、台湾の中華航空も飛ばなくなった。いずれも戦闘による被害を恐れての措置だった。残るアメリカやフランスの航空会社はなお運航を続けていたが、いつ停止となってもおかしくないという状況だった。
この動きにあわせて大使館の閉鎖や要員の縮小が始まった。24日からイギリス、オーストラリア、西ドイツ、オランダなどの大使館がいずれも多くの館員を撤退させ始めた。アメリカ、フランス、さらには日本、韓国などの大使館も機能は停止しなかったが、館員の人数は減らしていた。
外国での生命の危険となると、やはりその人間の帰属する国家の責任となる。政府が自国民の安全を確実にするというのは主権国家の基礎的な規範だともいえよう。だから南ベトナムの危機下での日本人の安全は日本政府が配慮するわけだ。では具体的にどうするのか。
4月中旬の時点で南ベトナムに滞在、あるいは居住する日本人は約150人とされた。そのうち日本大使館関係者が約30人、報道関連が40人ほど、その他、一般日本企業の駐在員関連や長期居住をしている元日本軍将兵の人たちなどが80人ほどという内訳だった。その大多数が首都のサイゴン地区に滞在していた。これら日本国籍の男女の安全を保つ責任は日本政府にあるということなる。もちろんどんな場合でも個人の言動はまずその個人の責任という部分があることは言わずもがなである。だが公式には日本大使館が主体となって南ベトナムの日本人の安全の確保、そのための撤退の作業を進めることになった。
日本政府は4月中旬、南ベトナム在の日本人を退避させるため特別の救援機を飛ばすことを決めたのだった。この当時はまだ政府専用機とか自衛隊の民間人救出機はなかった。だから日本政府が民間の日本航空に依頼して、特別の救援機を飛ばすという計画となった。だが厳密にどの時点で、という見通しは立てられなかった。
そんな状況下の4月23日には南ベトナムに残っている日本人記者たちの進退をどうするかを協議する各報道機関の代表の会合が東京で開かれた。各新聞社やテレビ局からはほとんどが外信部長が出席しての協議だった。その会合での合意はすぐにサイゴンにいた私たち取材記者たちにも伝えられた。
「南ベトナムにいる日本人記者は日本政府が調達する日本航空の特別救援機がサイゴンに着けば、全員が同機に乗って国外に退避する」
この合意は私にとって衝撃的だった。戦闘の危険が迫れば、救援機が飛んでくる。ベトナム戦争は最後の歴史的な終局を迎える。だが現地の状況を必死で報じてきた日本人記者はその最後は見届けずに、避難するというのだ。日本に本社をおくメディア組織の立場を考えれば、一面、理解できる対応でもあった。とにかく日本人記者の安全が図られねばならない。実際にベトナム戦争では日本人ジャーナリストが何人も命を失っていたのだ。
同時に日本の新聞やテレビにとっては「他社見合い」という不文の慣行があった。特定の報道にあたる複数の日本メディアが足並みをそろえて一斉に行動することだ。一部の日本メディアだけが危険をかえりみずに報道にあたり、他のメディアは撤退してしまうという不平等は困るのである。だからこんな危機に対しては各社の代表が集まって、合意を目指すのだ。ただしアメリカやフランスなど外国のメディアが残って、歴史的な展開をどんどん報道しても、日本メディア間の平等が保たれば、問題なしとされるのである。
しかし現地ですでに3年もこの戦争を報じてきた私にとって、サイゴンに危険が迫った、救援機が飛来した、というだけで、他の日本人記者全員とともに現地を離れることには、どうにも抑えきれない抵抗があった。ベトナム戦争の歴史的な最終場面を目前にしながら、それを見ずに退却してしまう、というのでは、なんのための報道活動だったのか、ということになる。
ところが東京でのこの各社外信部長による協議には一つ、大きな欠陥があった。この協議の前提はサイゴンに真の危機が迫った場合、日本人記者にとっての国外退避の方法はただの一つ、この日航特別救援機に載ることだけだ、という認識だった。だが現実にはさらに最後の最後の国外脱出の方法が日本人記者にとっても開かれていたのだ。それはアメリカ大使館が緊急避難用の米軍ヘリコプターを動員して、合計200人ほどの外国人ジャーナリストたちも国外へ運ぶ、という計画だった。アメリカ政府が最終場面で米軍ヘリを使っての避難計画の主対象はもちろんアメリカ大使館の館員や関連の軍人軍属だった。だがさすがは超大国、そのヘリ部隊は同盟国や友好国の大使館員、さらには外国人ジャーナリストもある程度の人数、ピックアップするという人道主義ともいえる対応を示していたのだ。
そのためには外国記者の総会的な集まりの代表がアメリカ大使館と密接な協議を重ね、いざ避難の際の集合場所などまで決めていた。だが日本のメディアの多くはそのことを知らず、日本の特別救援機だけが最後の手段だと考えていたのだ。
そんな背景の下、4月25日、サイゴンの日本大使館で日本報道機関の現地の代表が集まった。日航機に全員が乗るという東京での決定に現地要員としてどう対応するか、大使館側とも協議することが目的だった。大使館からはこの日本人避難計画を担当していた渡辺幸治参事官、そして日本航空のサイゴン支所の間淳所長も同席して、議事の進行にあたった。実はこの2人は米軍ヘリでの避難計画も知っていて、日本の報道陣も日航機には全員は乗らず、各社1人ぐらいは必ず残るだろうと推測していた。そのために日本大使館として館員と報道陣と合わせて30人ほどを最後の米軍ヘリに乗せてもらうという要請をアメリカ大使館に伝え、イエスという回答を得ていた。だから実際には日本人記者には外国記者団からの要請と、日本大使館からの要請という二つのルートで米軍ヘリへの依存の道が少なくとも理論的には存在したのである。
しかし大使館の渡辺参事官らは米軍ヘリの計画については日本側メディアにはあえて知らせていなかった。知らせれば、せっかくの日本航空の救援機に乗る人間が減ってしまうと考えたからだ。しかもこの日本大使館での会合で各社の記者たちの感触を探ると、ほとんどの人たちが米軍ヘリのルートについて知らないことが判明した。だから私は思い切って、みなにその計画の存在を知らせた。渡辺参事官も「日本人合計30人分のヘリ搭乗はアメリカ大使館も認めてくれています」と明言した。すると各社の記者たちは一様に反応した。
「なんだ、それなら日航機に全員が乗る必要はなく、各社1人ぐらいはなお残留できるではないか」
その場の会合でその線での合意が成立し、サイゴン駐在の日本人記者団として改めて人見宏大使に米軍ヘリへの搭乗の確認を頼んだ。人見大使は「アメリカに頭を下げるのは本意ではないが」と苦笑しながらも、その要請を確約した。その結果、報道各社の記者1人だけは日航機が出た後も現地に残り、最後は米軍へりの日本人用30人分のなかに含めてもらう、という希望がまとまった。その旨を各社の特派員が本社に伝えた。東京でまた各社の外信部長会が開かれ、翌4月26日には決定変更が送られてきた。
「各社の記者はサイゴン常駐特派員1人を残して全員が日航救援機に乗り、避難する。残留特派員は米軍の最終ヘリで脱出する」
毎日新聞のサイゴンの常駐特派員は私である。だからこの決定変更で私にとっての、いつ、どうやって逃げるのか、あるいは逃げないのか、という課題は当面、解決されたように思えたのだった。
(つづく)
トップ写真:米海兵隊が南ベトナムのタンソンニャット空軍基地でアメリカ人とベトナム人を避難させている様子(1975年4月南ベトナム・サイゴン)出典:Dirck Halstead/Liaison
あわせて読みたい
この記事を書いた人
古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授
産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧