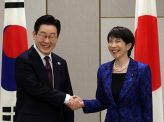ロサンゼルスの怒り、トランプの確信犯――歴史は繰り返すのか

宮家邦彦(立命館大学 客員教授・外交政策研究所代表)
宮家邦彦の外交・安保カレンダー 2025#23
2025年6月9-15日
【まとめ】
・トランプ政権がカリフォルニア州の同意なく州兵・海兵隊をロサンゼルスに派遣し、移民政策への抗議デモが激化した。
・州知事は派遣を違法とし連邦政府を提訴する意向を示し、事態は法的・政治的対立へと発展。
・ロサンゼルスの歴史的な暴動と重ね合わせ、今回の強硬措置が過剰であるとの批判も。
韓国大統領選も終わり、今週はあまり大きなニュースはないかな、などと思っていたら、やっぱりトランプ政権は「期待?」を裏切らなかった。いつもの通り、日本時間早朝CNN・USをチェックしていたら、ロサンゼルスでトランプ政権の移民政策に反対する大規模抗議デモが発生、多くの逮捕者が出たという。でも、それだけなら大したことはない。問題はトランプ政権の動きである。
抗議活動が始まったのは6日夜だったが、騒ぎが拡大したのは8日、現地の州知事や市長の了解を得ない中、トランプ氏が州兵を派遣する決定を下してからだ。知事は州兵派遣を違法とし撤退を要求、9日には州兵派遣で連邦政府を提訴する意向を表明した。これに対し、トランプ政権は海兵隊700人の一時的派遣も決めたそうだ。それにしても、なぜ海兵隊なのか?
理由は「州兵増員までの措置」で「連邦政府職員と財産を守るため」というが、国内で米軍を使うには「内乱法」を発動する必要がある。更に、トランプ氏は民主党のカリフォルニア州知事やロサンゼルス市長などの逮捕を支持する考えまで示唆したそうだ。州知事の同意なき州兵派遣は、法的には可能らしいが、60年ぶりの異例事態だという。
ロサンゼルスといえば、あのドジャースの本拠地、今の日本人のイメージは決して悪くない。だが、歴史的にこの街では暴動が頻発している。特に有名なのは1965年のワッツ暴動と1992年のロサンゼルス暴動だ。いずれもかなり大規模なもので、多くの死傷者が出ている。まずは前者のワッツ暴動から。
1965年8月、ロサンゼルス南部のワッツ地区で、白人のハイウェイパトロールとロサンゼルス市警察が、飲酒運転の疑いでアフリカ系青年とその母親を逮捕しようとした際に、現場に居合わせたアフリカ系住民が警官の行動に怒りを爆発させ、暴動へと発展したという。6日間続き、死者34人、負傷者1,000人以上、逮捕者4,000人以上を出した。
続いては ロサンゼルス暴動だが、これは筆者がワシントン在勤中の事件なので鮮明に覚えている。1991年3月、アフリカ系男性ロドニー・キングがスピード違反で逮捕された際、4人の白人警官から激しい暴行を受けたが、翌1992年の裁判では警官たちが無罪となったことにアフリカ系コミュニティが怒りを爆発させた。
死者50人以上、負傷者2,000人以上、逮捕者1万人以上を出し、特にコリアンタウンでは多くの店舗が破壊され、多額の損害が出たという。それに比べれば、という訳ではないが、今回は人種暴動というより、移民規制反対だから、ヒスパニック系の方が怒っているのかも。しかし、一部で車両放火や略奪行為が発生したものの、今のところ「大暴動」とは言い難いだろう。少なくとも、州兵や海兵隊を投入するレベルではない。
こうなると、トランプ政権の動きは「確信犯」というべきだろう。機会を逃さず、わざわざ敵対者を挑発し、不必要な強硬手段を講じて、支持者たちにアピールしつつ、メディアを翻弄する。いわゆる「スピン・ドクター」の一種だが、ここまで来ると「お見事」を通り越して、「それをやっちゃー、おしめーよ」ではないかと愚考する。
さて続いては、いつもの通り、欧米から見た今週の世界の動きを見ていこう。ここでは海外の各種ニュースレターが取り上げる外交内政イベントの中から興味深いものを筆者が勝手に選んでご紹介している。欧米の外交専門家たちの今週の関心イベントは次の通りだ。
6月10日 火曜日 アルゼンチン大統領、イスラエル訪問(3日間)
オランダ首相訪独、独首相と会談
バングラデシュ暫定政権首席顧問、訪英
インド外相、欧州委員会委員長と会談(ブラッセル)
6月11日 水曜日 ポーランド議会、信任投票
6月12日 木曜日 NATO事務総長訪伊、伊首相と会談
6月14日 土曜日 ワシントンで軍事パレード
6月15日 日曜日 カナダでG7首脳会議(3日間)
デンマーク首相と仏大統領がグリーンランドを訪問
最後にガザ・中東情勢について一言。9日、米大統領はイスラエル首相と電話会談した。詳細は不明だが、報道によれば、トランプ氏はホワイトハウスでイランとの交渉に関し、”We’re doing a lot of work on Iran right now,” “It’s tough … They’re great negotiators.”と述べたそうだ。さすがはイランである。
一方、イスラエル首相は「米大統領と話した。彼はイランとの協議が今週末も続くと述べていた」とのみ語った。まあこれだけでは分からないが、筆者の勝手な見立てはこうである。
●米イラン協議は佳境にあり、特にウラン濃縮度をめぐり意見が対立しているが
●恐らく米側はイスラエルに協議の詳細を伝えていない可能性があり
●しびれを切らしたネタニヤフがトランプに電話を掛けたのではないか
●イランはギリギリの合意を欲している筈だから、交渉はまだまだ続くだろう
●トランプ・ネタニヤフ電話会談でイスラエルの対イラン攻撃の可能性が高まるとは思えない
というものだ。今週はこのくらいにしておこう。いつものとおり、この続きは今週のキヤノングローバル戦略研究所のウェブサイトに掲載する。
トップ写真:gettyimages by Mario Tama
あわせて読みたい
この記事を書いた人
宮家邦彦立命館大学 客員教授/外交政策研究所代表
1978年東大法卒、外務省入省。カイロ、バグダッド、ワシントン、北京にて大使館勤務。本省では、外務大臣秘書官、中東第二課長、中東第一課長、日米安保条約課長、中東局参事官などを歴任。
2005年退職。株式会社エー、オー、アイ代表取締役社長に就任。同時にAOI外交政策研究所(現・株式会社外交政策研究所)を設立。
2006年立命館大学客員教授。
2006-2007年安倍内閣「公邸連絡調整官」として首相夫人を補佐。
2009年4月よりキヤノングローバル戦略研究所研究主幹(外交安保)
言語:英語、中国語、アラビア語。
特技:サックス、ベースギター。
趣味:バンド活動。
各種メディアで評論活動。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧