自分の“編集モデル”を見つめよう

為末大(スポーツコメンテーター・(株)R.project取締役)
【まとめ】
・自分の認識を編集して意味づけすることを“編集モデル”と呼ぶ。
・自らの“編集モデル”に距離を取れなくなって一色に染まってしまうと「原理主義」に陥ってしまう。
・私たちはあくまで“編集モデル”を選んでそれを使っているという認識が大事。
私の本はよく自己啓発の領域に置かれることが多いので、自己啓発と言われる本を読んでみると、つまるところ”編集モデル”を提供するのが自己啓発なんだろうと思います。
自分にとって世界とは、実際に存在していて、それを自分が認識して、さらに好ましいとか好ましくないとか編集して意味づけする、という三段階で成り立っていると思います。
実際に存在しているものを変えるのはなかなか大変だし、変えられないものも多いのでアプローチが難しい。また認識はほぼ無意識の領域なのでこれも変えられない(変えられるという自己啓発書もありますが)。なので編集モデル領域でなんとかしましょうということになる。
よく努力か環境かという議論がスポーツではなされます。努力の世界は、全ての問題につべこべ言わず自分の努力でなんとかすべきだしなんとかなるはずだということかなと思います乱暴に言うと。
環境の世界は、人間がそうなるには、環境要因の方が大きい。多くのアスリートはまず才能を持って生まれ、才能を伸ばすような環境で育ち(トップアスリートは幼少期に競技環境があった確率が高い。また4,5,6,7月生まれが多い。兄弟で言えば真ん中が多い)、努力できるような自信を育む環境にいたから頑張れたのだ。だから頑張れない人は個人の努力の問題だけではないということかなと思います。
最近、“OUR KIDS”というアメリカの教育格差と経済格差がこの50年でいかに開いていったかという本を読みましたが、ここまでくると個人の努力で説明するのはなかなか難しいなという印象を抱きました。
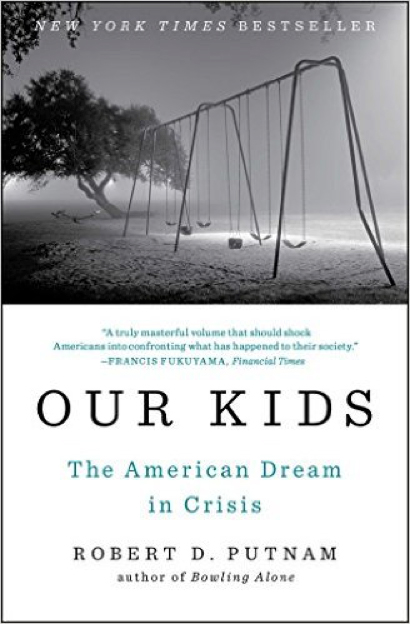
Our Kids: The American Dream in Crisis by Robert D. Putnam
「邦題:われらの子ども:米国における機会格差の拡大」 出典)amazon
ただ、だからと言って自分のせいじゃないという編集モデルを持って生きることが望ましいかというのは別の話です。例えば人間には自由意志は存在しないという説明を受けた後、人の振る舞いは多少反社会的になるという実験結果があります。実際に自由意志が存在するかどうかと、存在することにしておくかどうかは別の話で、仮に幻でも信じておいた方が社会が円滑に動く幻も存在すると私は思っています。
一方でこの編集モデルは厄介のところもあり例えば、強くあらねばならないという強固なモデルを持って育った人間は、ある厳しい局面で自分の弱さをみてしまった時に、ひたすらに自分を責めるということにもなりかねません。
数例しか知りませんが、鬱になってしまったり精神的に追い詰められやすい人は、まず編集モデルに無自覚でありかつかなり強固な編集モデルを持っているように思います。
猫は絶対許せないと思っている人がある日自分は猫だったと気づいた時に、猫も悪くないなと考えられず、ずっと猫である自分を責め続けながら、一方でそんなはずはないとモデルにしがみつきながら、境目をさまようわけです。
全ての人間は編集モデルの世界を生きているわけですが、あくまでモデルなので、本当はどんなモデルでもいいわけです。わかりやすいモデルを提供して来たのが宗教だったのだと思います。さすがに長期間淘汰に耐えただけあって、皆がそれを信じた時にはちゃんと社会が円滑に回りやすいようになっているのではないでしょうか。
歴史上新たな編集モデルが誕生するたびに、ついに真実が明らかになったと言われるわけですが、実際のところは新たな編集の仕方の提示があったということなんだろうと思います。
人生は生きやすいように、どの編集モデルが合うかを選んで、それをインストールするかということだろうと思います。私が大事だと思うことは、私たちはあくまで編集モデルを選んでそれを使っているという認識です。
猫は猫でしかないんですが、それを嫌うような編集モデルと、好むような編集モデルがぶつかった時に、厄介なことが起こりやすいと感じています。
編集モデルがない世界には善も悪も意味もありません。全部こっちが勝手に編集しているだけです。原理主義とは編集モデルに距離を取れなくなって一色に染まってしまうことなんだろうと解釈しています。
(この記事は2017年7月1日に為末大HPに掲載されたものです)
※記事中の画像が表示されない場合は、http://japan-indepth.jp/?p=35464で記事をお読みください。
あわせて読みたい
この記事を書いた人
為末大スポーツコメンテーター・(株)R.project取締役
1978年5月3日、広島県生まれ。『侍ハードラー』の異名で知られ、未だに破られていない男子400mハードルの日本 記録保持者2005年ヘルシンキ世界選手権で初めて日本人が世界大会トラック種目 で2度メダルを獲得するという快挙を達成。オリンピックはシドニー、アテネ、北京の3 大会に出場。2010年、アスリートの社会的自立を支援する「一般社団法人アスリート・ソサエティ」 を設立。現在、代表理事を務めている。さらに、2011年、地元広島で自身のランニン グクラブ「CHASKI(チャスキ)」を立ち上げ、子どもたちに運動と学習能力をアップす る陸上教室も開催している。また、東日本大震災発生直後、自身の公式サイトを通じ て「TEAM JAPAN」を立ち上げ、競技の枠を超えた多くのアスリートに参加を呼びか けるなど、幅広く活動している。 今後は「スポーツを通じて社会に貢献したい」と次なる目標に向かってスタートを切る。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧
































