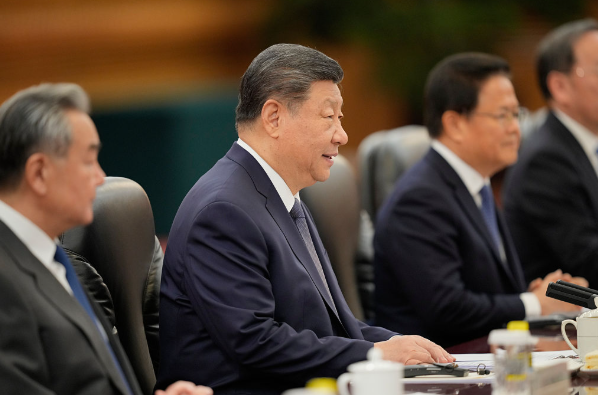アフガニスタン危機の日本への意味(中)

古森義久(ジャーナリスト・麗澤大学特別教授)
「古森義久の内外透視」
【まとめ】
・アフガニスタン、タリバンが攻勢。首都カブールに迫る。
・米バイデン政権のアフガン離脱に、議会で反対の声。
・民主主義国家だからこそ国内の世論を優先するしかなく、結果、同盟相手への配慮はどうしても二次的、三次的になってしまう。
私がいま駐在するアメリカの首都ワシントンではアフガニスタン情勢の危機が幅広い関心と懸念を集めている。一般アメリカ人にとってもアフガニスタン共和国の命運は自国への9・11同時多発テロとからんで非常に気になる対象なのである。
なにしろアメリカの歴代政権は過去20年にもわたり、イスラム原理主義のタリバン勢力と戦ってきたのだ。
アフガニスタンで戦闘任務を経験してきたというアメリカ軍人たちの数も多い。戦死者、負傷者も少なくない。だがバイデン大統領はその戦いをいまやすべて終結することを宣言したのだ。
そんな情勢下でアフガニスタンの第二の都市カンダハルがタリバン側の支配下に入ったという報道はアメリカ側にとってとくに衝撃的だった。なぜならこの都市はタリバンにとっての誕生の地、聖地でもあったからだ。
カンダハルはアフガンの首都カブールから南西へ500キロ近く、タリバン(求道者、あるいは学徒という意味)の本拠地だった。タリバンが武装した政治、宗教勢力としてアフガニスタンのほぼ全土を支配した1996年から2001年までの期間も、形式的な首都はカブールとしながらも、最高指導者のムッラー・ムハンマド・オマル師らはカンダハルにいて、そこから指令を出していた。
だから2002年までにアメリカ軍の支援を得た反タリバン勢力がカンダハルを制圧した時は、支配勢力としてのタリバンの終わりとされた。
私が産経新聞記者としてのカブールでの取材を始めた2002年2月にもカンダハルはアフガン共和国政府側の支配下にあった。私はそのとき、タリバンについて皮膚感覚でも知るために、なんとかカンダハルに入りたいと願っていた。
だがカブールからカンダハルまでの主要道路沿いではなお戦闘が続き、危険度が高いことがわかり、みあわせたという体験があった。
そんなタリバンの象徴の都市が過去20年ほどのアフガン政府の支配を離れて、あっけなくまたタリバン側に戻ったという報道には驚かされたわけである。これこそタリバンの最終勝利をすでに予兆したのではないか、という実感だった。
8月14日付のワシントン・ポストは一面の中央に「タリバンが敏速な前進、アメリカは退避を動員」という大きな見出しの記事を載せていた。タリバンがついに首都のカブールまで迫ってきたので、アメリカはもっぱら自国の大使館や要員を退避させることに忙殺されるようになった、という内容の記事だった。
アメリカがまさに敗北して、脱出する、という感じの報道だった。

写真)米諜報機関や軍の通訳として働いていたアフガニスタン人(中央)らは、特別移民ビザ(SIV)プログラムの一環として米国に来ることを申請している。アフガニスタン、クナー州 2021年7月26日
出典)Handout Photo/Getty Images
ニューヨーク・タイムズは前日の8月13日付に歴代政権のアフガン政策の顧問役を務めた著名な戦略専門家のフレデリック・ケーガン氏の寄稿論文を載せていた。バイデン政権の唐突で急激なアフガン撤退を厳しく非難する内容だった。
論文の見出しは「バイデンはタリバンを阻止できた」となっていた。そして「長年の同盟相手をこんなふうに放棄することが自由世界の指導者を自認するアメリカ、そしてバイデン大統領のすることなのか」と問いつめていた。
アメリカ国内でも、とくに議会を中心として今回のバイデン政権のアフガン離脱の手法に反対する声は広範なのである。
アフガニスタンでアメリカの政策に同調し、協力してきた国民たちは反米のタリバンがまた全土を支配すれば、報復や制裁を受けると恐れて、首都カブールからアメリカの支援を得て、国外に脱出するという実例があいついでいた。アメリカ側もこの種の人たちまで放棄するわけにはいかず、避難に全面協力するようにみえた。
そこで私がどうしても連想したのはベトナム戦争の最終段階での南ベトナムからの国民多数の脱出の光景だった。もう46年も前の1975年春だった。
当時の南ベトナムの首都サイゴン(現在のホーチミン市)に向かっては北ベトナム軍の大部隊が進撃を速めていた。
私はその3年ほど前から毎日新聞のベトナム駐在特派員として戦争の報道にあたっていた。南ベトナム、つまりベトナム共和国の首都からの報道だった。その3年の間に北ベトナムが南ベトナムに大部隊を侵入させ、南ベトナム政府軍とアメリカ軍を敵にして激しい攻撃をかけ続けた。1972年ごろからの動向だった。
共産主義の北ベトナムはソ連と中国に全面支援されていた。一方、南ベトナムはそもそもアメリカによって支えられた国家だったが、私が報道にあたった北ベトナム軍が南の各地で打ち上げた1972年大攻勢で引き分けのような状態となると、アメリカはもう南ベトナムから全面撤退することを決めてしまった。
アメリカのこうした唐突な動きは民主主義国家だからこそだともいえた。国内の世論が一定方向に強くなれば、政府やその勢いに従うほかない。共産党一党支配の独裁国家にはこのパターンはない。
アフガニスタンに対してもこんどのアメリカの態度は似ていた。国内の世論を優先するしかない。その結果、これまで緊密に手を結び、永遠とも思える長期の支援を誓ってきた同盟相手への配慮はどうしても二次的、三次的になってしまうようなのだ。
このあたりにいまのアフガニスタンの悲劇があるのだといえる。
(下につづく。上はこちら。全3回)
トップ写真)首都カブールの仮設キャンプで、援助物資に手を伸ばす避難民 アフガニスタン・カブール 2021年8月10日
出典)Photo by Paula Bronstein /Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授
産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧