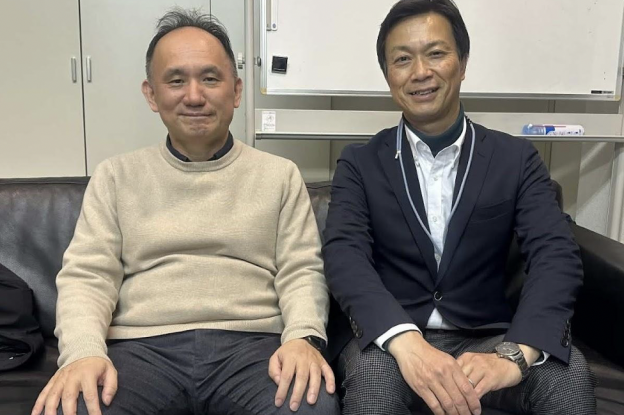地域住民の命を守った鹿島厚生病院渡邉善二郎院長

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)
「上昌広と福島県浜通り便り」
【まとめ】
・福島県南相馬市は、鹿島厚生病院の渡邉善二郎院長の存在抜きには語れない。
・東日本大震災直後、医療スタッフの避難により病院機能が継続できなくなった。
・残ったスタッフと戻ったスタッフをまとめ、診療を継続し地域住民の命を守った。
先月、南相馬市を訪問し、東日本大震災から12年を振り返る話をしてきた。お呼びいただいたのは鹿島厚生病院の渡邉善二郎院長だ。今の南相馬市があるのは、渡邉院長の存在抜きには語れない。あまりメディアが取り上げることはなかった東日本大震災直後の現地の状況をご紹介しよう。
鹿島厚生病院は、福島県厚生農業協同組合連合会(厚生連)が運営する病床数80床の病院だ。内訳は、一般病床40と療養型病床40だ。決して、病床数は多くないが、南相馬市鹿島区に存在する唯一の病院であり、地元住民にとってはなくてはならない存在だ。
私が渡邉院長と知り合ったのは、立谷秀清相馬市長の紹介だ。2011年4月20日、立谷秀清相馬市長の自宅で初めてお目にかかり、翌21日に病院を訪ねた。平日なのに病院は閑散としていた。院内も電気が消えており、数名の事務員が忙しそうに働いているだけだった。
震災後、病院機能は完全に閉鎖したが、4月11日から一部の外来は診療を再開していた。渡邊院長は外来診療の合間をぬって、私たちと情報交換をしてくれた。
私は被災地で活動する上で、「言いっぱなしの提言だけ」は絶対にやらないと決めていた。先方が抱える個別の問題を一緒に考え、自分たちも実際に動きたいと思っていた。
私は、渡邉院長にお会いすると、「我々で何かお役に立てることがあるでしょうか」と聞いた。そこで返ってきた答えは「入院を再開したい」だった。「医師が不足している」でも、「医薬品が足りない」でもない。
脱線するが、鹿島区の置かれた状況を、少し説明しよう。鹿島区は南相馬市の最北部に位置し、北の相馬市と南の原町区に挟まれる人口1.2万人ほどの地域だ(当時)。2006年(平成18年)に小高町、原町市と合併し、相馬郡鹿島町から南相馬市鹿島区となった。
町名の鹿島の由来は、市街地の中心部にある鹿島御子神社に由来する。常陸の国の鹿島神宮の祭神、武甕槌命(タケミカヅチ)の御子神を祭っているため、この名前がついた。日本武尊が東征した折には、武運長久を祈るため、この神社に詣でたというから歴史は古い。
鹿島区の中央部には真野川が流れる。市街地の大部分は沖積平野だ。水が確保しやすかったのだろう。この地域は、早い時期から稲作が行われた。江戸時代までは相馬藩が領有し、相馬藩七郷の一つ「北郷」と呼ばれ、米作の中心地であった。現在も米作を中心とした農業が主産業である。
鹿島区は、南相馬市の中では福島第一原発との距離が最も遠い。中心部で約33キロ離れている。当然だが、南相馬市の中では放射能汚染の程度は最も低い。
しかしながら、そんなことが分かったのは、原発事故からかなり経ってからだ。事故当初の混乱ぶりは、南相馬市内の他の地域と大差なかった。鹿島厚生病院のスタッフの中には「水素爆発の音が聞こえた」という人もいる。私の知る限り、原発から23キロに位置する南相馬市立総合病院のスタッフは誰も水素爆発の音は聞いていないので、この話の真偽は不明だ。ただ、当時、病院スタッフが極度の恐怖・緊張に苛まれていたのは確実だ。
原発事故の話を聞いて、多くの医療スタッフは避難を始めた。事故後、「無断」で欠勤した人までいた。多くは原発20キロ圏内の小高区在住や津波で自宅を失った人だ。当時の状況を考えれば無理もない。
3月15日、鹿島厚生病院は職員の避難を自主的な判断に任せることに決定したところ、翌16日には職員の数が半減した。経営する厚生連は、病院再開まで職員を「特別有給休暇」扱いにして事後処理したという。
理由は何であれ、医療スタッフが確保出来なければ、病院業務は継続できない。特に、重症患者を治療する入院業務は立ちゆかない。渡邊院長は「病院は診療を続けることができなくなり、自衛隊に患者を会津まで運んで貰いました。その際に、この病院は「みなし30キロ圏内」と認定されました」と言う。
ただ、原発事故から時間が経つと、鹿島区の線量は低いことが明らかとなった。また、原発から30キロ以上離れていたため、避難や屋内退避などの規制地域にも指定されなかった。
やがて、鹿島区の住民は自宅に戻ってきた。また、原発20キロ圏内の小高区に住む人々も、鹿島区の避難所に移ってきた。この結果、鹿島区には膨大な数の高齢者や病人が集まった。
このような動きは医療スタッフも同じだ。多くの医療スタッフが病院に戻ってきた。政府の指示ではなく、医療スタッフの避難により病院機能が継続できなくなったのは、私の知る限り、鹿島厚生病院だけだ。
医療従事者としては、罪の意識を拭えなかっただろう。残った看護師と逃げてしまった看護師の間で軋轢が生じても当然の状況だった。ただ、渡辺院長は、彼らを上手くまとめた。渡邊院長は「避難を決めた職員は、申し訳ないと涙し、残った職員は、私があなたの立場なら、避難すると理解を示していました。避難した職員は、避難先で何故職場を放棄してしまったのかと悩み、復帰後は、この先何があっても職場を離れないと多くの者が語っていました。これが士気の高さだと考えました。そして、看護師はほぼ全員が戻ってきてくれました。」と言う。渡邊院長のリーダーシップの元、震災前から素晴らしいチームワークができあがっていたのだろう。
入院診療再開に向け、鹿島厚生病院関係者は様々な部署に陳情した。当初、「厚労省が規制している」と考えていたため、地元選出の国会議員などを通じ、厚労省に陳情した。しかしながら、厚労省は「福島県の方針です」と言うだけで、具体的に動くことはなかった。確かに、鹿島厚生病院を「みなし30キロ」に認定したのは福島県であり、厚労省の管轄ではない。厚労省の言い分も一理ある。
次に病院関係者は、福島県に様々なルートを介して陳情した。しかしながら、福島県は入院再開を頑なに認めなかった。その理由はわからない。
南相馬市立総合病院のように、原発30キロ圏内の病院を再開するのは、政府との調整など手間を要するだろう。
一方、鹿島厚生病院は、福島県が30キロ圏相当と見なしただけだ。福島県の判断で方針を変えられる筈である。このあたりの情報については、当時、厚労省の政務官を務めていた梅村さとし参議院議員が情報を入手してくれた。福島県が気にしたのは、何らかの面子か、他の政策との整合性だったのではなかろうかということだ。
もし、そうだとすると、福島県にいくら頼んでも無意味だ。私は渡邊院長に、「問題を出来るだけ多くの人に知って貰うようにしましょう。社会に知って貰うには、メディアに言うのが一番だ」と繰り返しお伝えした。役所が動かないときは、外圧が一番だ。メディアを通じて、社会が問題を認識すれば、政府は驚くほどのスピードで対応する。
私も旧知の記者たちに、鹿島厚生病院の窮状をメールで伝えつづけた。ただ、この時に苦労したのは、南相馬市を取材している記者があまりにも少なかったことだ。多くのマスコミは、新聞記者の被曝を問題視して、原発周囲への取材を禁じていた。取材に入るときは、上司の許可、および取材後の健康診断を義務づけたという。知人の記者は「組合問題など関係するのでしょうね。要は上が責任をとりたくないだけですよ」と語った。
ただ、メディアの中にも気骨のある人はいた。現地で活動する我々にコンタクトしてきた人がいた。それは読売新聞の加納昭彦記者だ。常磐線原ノ町駅前の、一軒だけ営業を続けている定食屋で会うこととなった。南相馬市の医療機関の窮状を理解して貰いたく、懸命に説明した。加納記者は、初めて知る情報が多かったようだった。
福島支局の記者の多くは、普段からネタを貰っている福島県庁に気兼ねする人が多い。彼は東京本社の医療情報部に所属する記者だ。何の気兼ねもなく、問題点をストレートに書いた。
4月27日の読売新聞総合面に「地元で入院できない 福島第一原発30キロ圏で規制 救急搬送1時間超」という大きな記事が出た。これ以降、関係各所に問い合わせが殺到したのだろう。即座に入院規制が解除された。改めてマスメディアの影響力の大きさを実感した。

▲写真 常磐線 原ノ町駅周辺の定食屋で。左から加納昭彦記者、高橋幸江医師(東京都立駒込病院)、筆者、松村有子医師(東京大学医科学研究所)2011年4月29日(執筆者提供)
鹿島厚生病院の入院再開を巡る騒動は示唆に富む。なぜ、民間の医療機関が入院を再開するのに、県の許可が必要だったのだろうか。厚労省の知人に聞いたが、「おそらく法的根拠はないだろう。医療法に基づけば、県が個別の医療機関の営業を指示する権限は無いはずだ」という。後日、知人の記者が福島県に問い合わせたところ、「こちらからは指示していない」と回答したようだ。私は、震災直後の混乱を考慮すれば、福島県の対応は仕方がなかったと思う。当事者能力を失った病院を、福島県がサポートしたことは褒められてしかるべきだ。
問題は状況が変わった後に、柔軟に対応できなかったことだ。なぜ、こんなことになるのだろうか。福島県幹部と厚労官僚は「もし原発事故が再発すれば、自分たちが患者を搬送しなければならない」と主張し、全く動かなかったらしい。これじゃ、有事の際に病人を搬送するのが面倒なので、弱者を見捨てたと言われても反論できない。県や厚労省に震災時に病床数を制限する法的権限はないのだから、役人が福島県民の無知につけ込んで、「超法規的」に対応したことになる。
また、地元の医療機関が福島県に怯えていたことも関係する。当時、福島県の医師数は人口1000人当たり1.8人で、全国37位だった。相双地区に限っては1.1人に過ぎなかった。これは、民族紛争を続けていたシリアやアラブなどの中東地域と同レベルで、高齢化を考えれば、相双地区の医師不足は中東より遙かに深刻だ。
福島県の唯一の医師養成機関は福島県立医大だ。福島県内の多くの病院は、福島医大の医局から医師を派遣して貰っている。このため、希少な医師の派遣力を背景に県全域を支配しているという見方も可能だ。現に、浜通りの病院幹部は「福島県の逆鱗に触れ、医師を引き上げられたら、地域医療は回らない」と言う。また、「東北大から医師を派遣するように頼んだら、県立医大から圧力がかかった(地元病院幹部)」などは日常茶飯事だ。
このような状況なら、福島県の役人が、「病院は何かするときには、県庁にお伺いを立てるのが当然」と信じ込んでいてもおかしくない。私には、大災害時でも、現地での判断ではなく、県幹部の思惑が優先されているように見えた。
ただ、部外者の私からみて、浜通りの医師が思うほど、福島県や福島県立医大は頼りにならない。東日本大震災で、医局員を引き上げたところはあっても、大量に医師を派遣し、被災地を支援したそぶりはない。
読売新聞の報道が効き、鹿島厚生病院の入院診療は5月2日から再開された。再開以降、私は何度か病院にお邪魔させて頂いた。
5月5日(子どもの日)に訪問した時、渡邊院長は当直中で、丁度、救急車が到着したところだった。患者は下痢が続いている高齢者だった。脱水が酷く、全身状態が衰弱しているため、入院となった。ウイルス感染による急性胃腸炎だろう。この患者で、入院患者数は14人目という。毎日4, 5人の患者が入院していることになる。
渡邊院長が診察している間、救急隊と話すことができた。「鹿島厚生病院が入院を再開して、多くの患者が救われています」と言ったのが印象に残った。
もし、鹿島厚生病院で入院できなければ、この患者は遠く福島市か、仙台市に運ばれていた。脱水状態の高齢者にとっては、相当な負担だ。途中で急変してもおかしくない。鹿島厚生病院の入院診療再開は、地元住民は勿論、救急隊員にとっても朗報だったようだ。
その後も入院患者は増え続けた。5月24日には、渡邊院長から「42名の方が入院しています(中略)。仮設病棟、仮設老健の件も厚生連、南相馬市、福島県に働き掛け進めていきたいと考えています」と連絡が入った。特に看護師の負担は多く、過労で倒れる寸前だという。
これが東日本大震災直後の福島の現状だ。この状況でスタッフをまとめあげ、診療を継続し、地域住民の命を守ったのが、渡邉院長だった。時の経過とともに、当時の記憶は薄らいできた。東日本大震災当時の福島で何が起こったのか、私は、この貴重な経験を後世に伝えていきたいと思う。
トップ写真:渡部善二郎院長と筆者 2011年4月21日。鹿島厚生病院にて(執筆者提供)
あわせて読みたい
この記事を書いた人
上昌広医療ガバナンス研究所 理事長
1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧