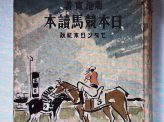「黄金の山羊(シェーヴル・ドール)に賭けた“極貧”の作家」文人シリーズ第5回「ヘミングウェイとパリの競馬場」

斎藤一九馬(編集者・ノンフィクションライター)
「斎藤一九馬のおんまさんに魅せられて55年」
【まとめ】
・ヘミングウェイが家計に困っていた証の一つが、競馬狂いではなかったのか。
・ヘミングウェイにとって、競馬は文字通り「副業」になった。
・『移動祝祭日』からは、ヘミングウェイの苦楽・呻吟の日々が偲ばれ、競馬ファンなら読んで損はない。
遺作『移動祝祭日』によれば、1920年代、作家アーネスト・ヘミングウェイ(1899~1961年)のパリ時代は極貧の生活で、大げさでなく食べるものにも困る暮らしぶりだった。それで思い出した。私にも、学生時代(1960年代)、えびせんと豆腐だけで1週間を過ごしたと豪語する先輩がいて、その青白い凄みを湛えた面貌(栄養失調)に、そこはかとなく尊敬の念を覚えた記憶がある。貧乏が勲章だった時代だ。
その頃のヘミングウェイは最初の妻エリザベス・ハドリー・リチャードソンと結婚していて、実は彼女の実家は相当裕福な家だったらしい。金銭的な支援もあり、本当は生活に困るような家計の状況ではなかったのに、なぜヘミングウェイが意図的に貧困生活を選び取ったのか? 貧苦の暮らしを演じたのか? それは『移動祝祭日』の訳者あとがきに詳しい。
家計に困っていた証の一つが、ヘミングウェイの競馬狂いではなかったのかと、私は勘ぐっている。20代前半という若さのヘミングウェイは、パリ西部のブローニュの森の中にあるオートウィユ競馬場に入り浸っては、入ったばかりの原稿料、すなわちなけなし(?)の生活費をなくしていたのは事実だ。
フランスの競馬場といえば欧州競馬の最高峰「凱旋門賞」の行われるロンシャン競馬場が有名だが、オートウィユ競馬場は障害レースのみで、ロンシャンと比べると地味な存在だ。だが、障害レースだけに落馬などのアクシデントが多く、高配当が続出して、地元の玄人ファンにはこちらのほうに人気があった。今日まで約150年の歴史を持つということが、なによりファンに愛され続けたことの証左であろう。
私も40年ほど前、フランスの競馬場を訪れたことがある。残念ながらロンシャンでもオートウィユでもなく、ロンシャンと同じくブローニュの森にあるヴァンセンヌという競馬場であった。馬の後ろに繋がれた繋駕(馬車)を走らせる繋駕レースが行われていて、これはこれで、痺れるスピード感には欠けるが、クラシックな優雅さがあり、面白かった。馬券は、安い配当の単勝を一枚とっただけで大負けしたと思う。今となっては少し自慢の懐かしい記憶だ。
ヘミングウェイはこのオートウィユ競馬場で有名なエピソードを残している。ほぼ毎日のごとく顔を出すヘミングウェイはやがて競馬場の係員や厩舎関係者と親しくなり、競馬場の時計係を任されるほどになったというから恐れ入る。ヘミングウェイは“人たらし”だったのだろうか。ヘミングウェイにとって、競馬は文字通り「副業」になった。
競馬場へは妻のハドリーを連れ出すこともあった。ある日の午後、ハドリーは賭け率1対120という超大穴、黄金の山羊(シェーヴル・ドール)という名の馬に夫婦の有り金全部を賭けた。競馬好きの夫婦によくあることだが、得てして妻のほうが博才も度胸もあることが多いのはどういうわけか・・・。
レースが始まると、シェーヴル・ドールはすぐ他馬を大きく引き離して独走態勢に入った。もうゴールは間近、このままいけば--
二人は立ち上がって山羊、いや馬の姿を追った。しかし、黄金の山羊は最後の障害で転倒して落馬。ふたりの半年分の生活費があえなく競馬場の空へ飛んでいった。
このヘミングウェイ夫妻と同じような悲劇を、その40年後に味わった日本人の作家がいる。寺山修司・九条今日子夫妻である。
「私たちは生活費とは別に、それぞれの競馬貯金を持っていました。寺山は引き出してすぐ本などを買ってしまうので、残額はいつも私のほうが多かったと思います」と九条は書く。ふたり仲良く競馬三昧の生活を楽しんでいたのだ。
「その頃の二人の唯一の無茶な遊びは、一九六六年のダービーでニホンピロエースの単勝を10万円買ったことです。大卒初任給が一万いくらという時代です」
ニホンピロエースは皐月賞を勝った尾花栗毛の美しい快速馬で、寺山はすっかり惚れ込んで、こう讃えている。「私は素晴らしい金髪を一人と一頭知っている。一人は死んだマリリン・モンローで、1頭はニホンピロエースだ」。
だが、ニホンピロエースはダービーで圧倒的な一番人気を裏切り、20着に沈んでしまった。九条は後に回想している。「競馬に絶対はない、ということをそれで学びました。(中略)今になって思えば、どこかで一度は馬券で大きく負けることが必要だったのかも知れません」。このあと、寺山は敗れていった馬たちを描いた珠玉のエッセイで名を成す。
話をノーベル賞作家にもどす。ヘミングウェイ夫妻はオートウィユ競馬場で大敗してしばらく経った頃、今度は、これもヘミングウェイがよく通ったアンギアン競馬場に向かった。よく晴れわたった日だった。競馬場の芝生にヘミングウェイの着ていたレインコートを敷き、持ち込んだワインを開けてランチと昼寝を愉しんだ。粋な遊びとはこういうことを言うのだろう。この日、ヘミングウェイは賭けた2つのレースで高配当の単勝を当て、だいぶ儲かった。「こういう日には稼いだ分の四分の一ずつを二人で分け、残りを次の競馬資金にまわした」とヘミングウェイは書いた。それを見て、私はちと不満だった。堅実すぎて、ヘミングウェイの豪放なイメージが壊れるのである。
時は流れて1996年正月の京都競馬場、例によって私は大敗した。最終レースが終わった後も放心の体で、第一コーナー近くの冷たい芝生の上に寝転がっていると、場内警備員に注意された。「早く、立ち上がって」。私にはそれが「早く、立ち直って」と聞こえた。私は着ていたレインコートの襟を立て、とぼとぼと入場門へ向かった。私の会社はその月末、倒産した。
寺山は「競馬は人生の比喩ではなく、人生が競馬の比喩なのである」と言った。ヘミングウェイは「競馬は人生の縮図である」と簡潔に決めた。一見、ふたりはまるで逆のことを言ったかのように見えるが、もちろん、言ったのはヘミングウェイのほうが先だ。ここは素直に、ヘミングウェイに一票投じたい。
ヘミングウェイの死後に発表され、事実上の遺作となった『移動祝祭日』からは、世に出る前のパリ時代、競馬三昧の苦楽・呻吟の日々が偲ばれ、競馬ファンなら読んで損はない。
参考文献:「太陽」1992年11月号、『移動祝祭日』(新潮文庫)
写真:左からアーネスト・ヘミングウェイ、ドナルド・オグドン・スチュワート。1930年頃。出典:photo by Bettmann/Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
斎藤一九馬編集者・ノンフィクションライター
宮城県生まれ。東京外国語大学インド・パキスタン語学科卒業。編集者・ノンフィクションライター。主な著作に『歓喜の歌は響くのか』(角川文庫)、『最後の予想屋 吉冨隆安』(ビジネス社)など。数誌に社会課題のルポルタージュを寄稿。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧