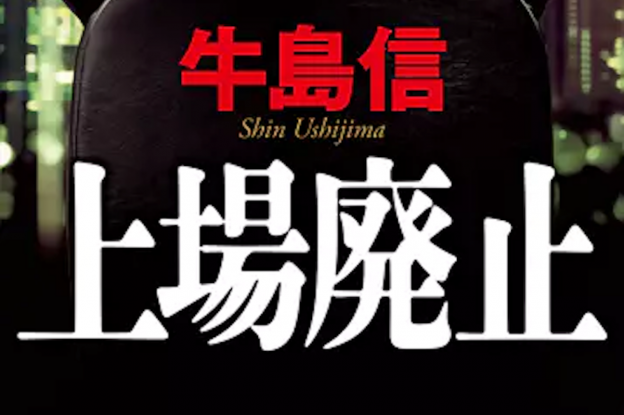牛島信著「年賀状は小さな文学作品」発売

【まとめ】
・筆者は、第二次世界大戦のヨーロッパ、アジアの勝利はアメリカの力が導いたと考える。
・しかし2025年現在、アメリカのGDPは減少し中国が台頭してきている。
・日本は「私的な潔癖や徳義にこだわって、本当の進歩を忘れていた」こと、これがすべての出発点だと筆者は思案する。
ジャパンインデプスでの連載の一部が、4月16日に『年賀状は小さな文学作品』と題して幻冬舎から発行される。安倍宏行さんのおかげである。そういえば2017年に出版された『少数株主』も安倍さんの激励のおかげで完成したのだった。この小説は日本社会に一定の影響を与え続けていると思っている。
並行して連載していただいていた「石原さんについての私的思いで」は、一足先に2023年5月、『我が師石原慎太郎』として同じ幻冬舎から出版された。それに続くのがこんどの『年賀状は小さな文学作品』という次第である。
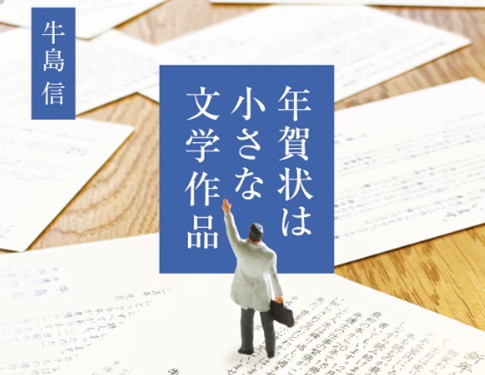
写真)『年賀状は小さな文学作品』牛島信 著
出典)幻冬舎
1996年から2025年までの30年間にわたる私の年賀状について文章を綴り始めたのは、いつのことだったか。
今回の本のなかにも書いているが、『舞踏会の手帖』という映画が昔あった。若い娘として20年前に社交界へデビューした女性が、未亡人になってしまってからその折の手帖を見つけ、その手帖に記されたダンス・パートナーたちを訪ねるという趣向の映画である。1937年のフランス映画で、監督したのがジュリアン・デュヴィヴィエ。といっても、知っている人はもう少ないだろう。
しかし、あのジャン・ギャバンが出た『望郷 ペペ・ル・モコ』を監督した方といえば、ああと思われる方もいるに違いない。
しかし、この『舞踏会の手帖』という映画が1938年の6月に日本で公開されたと知ると、がぜん興味が湧いてくる。1938年は昭和13年であり、2・26事件の翌々年、日華事変の翌年である。ましてや、この映画は1939年のキネマ旬報外国映画ベストテン第一位だったというではないか。戦前の日本人の生活は、当時まだそんなだったのだ。アメリカとの戦争が始まった翌年、1942年になって初めて上映禁止になったのだという。そのたった3年後には東京は大空襲にみまわれ、広島と長崎に原子爆弾が落とされた。
石原慎太郎さんに、その『舞踏会の手帖』という映画のタイトルに触れた小説があって、それがヒントになって、私は自分が何十年にもわたって出してきた年賀状巡りの文章を綴ってみようと思い立ったのだのだ。
それが今回は『年賀状は小さな文学作品』として二つ目の実を結んだというわけだ。もうひとつ、『団塊の世代の物語』が残っている。これも前回、一応の完結をみている。こちらの方は、題を含めて大いに推敲し、世を動かすことになる作品としての完成を期している。2025年の年賀状にも書いたとおり、「横の糸が老人の狂おしい恋、縦の糸が戦後80年史」である。
戦後80年は、1945年の第一の敗戦から1985年の第二の敗戦、そして2025年の第三の敗戦という40年間を区切りとした長いながい時間の流れである。その間に昭和20年に生まれた人間は80歳になっている。もういなくなっている人もいるだろう。
この小説のなかでは、第一の敗戦はアメリカへの敗北であり、第二の敗戦はプラザ合意を指し、第三の敗戦はセブン&アイの買収に始まる円安の日本がバーゲンセールを始めることになる。そしてそれが遂にコーポレートガバナンスをつうじて日本復活に到るという物語である。
私は、第二次世界大戦はヨーロッパでもアジアでも、アメリカの力が主導して勝利を導いたと思っている。アメリカで1941年3月11日に成立したレンドリース法(武器貸与法)がなければ、イギリスもソ連もあのようにドイツに勝利することはできなかったのではないかと考えているのだ。その直後である8月14日には、ルーズベルトとチャーチルによる大西洋憲章が生まれていることが、レンドリース法の意義を雄弁に物語っている。
後の世を生きている身からすれば、これで歴史は定まったのだと思えてならない。
殊に、ソ連へのレンドリース法による援助はあまり知られていないが、当時のソ連のトラックの7割を占めていたというから、これがなければスターリングラードは別の結果になっていた可能性が高かったとすらいえそうである。
それはそうである。アメリカは自国内での戦争がなく、軍需品の生産に励むことができた。これに比べてソ連はもちろんドイツもイギリスも陸続きの戦いをしていたのである。
その結果、アメリカは第二次世界大戦が終了した1945年、世界のGDPの半分を占めることになっていた。当時のアメリカ大統領は民間企業に対して軍需品の生産を支持する権限を有していたのである。要するに、GMやフォードに対して、民間用の車の生産を戦車の生産に切り替えることを命じたのである。
その「GDPの半分」が戦後の自由貿易体制を支える経済的理由であったということである。
いつの世でも、力のある者は自由を唱道する。昔のイギリスしかりである。
ところがそのアメリカのGDPは1985年には三分の一強となり、2025年には3割を切ってしまった。
1985年までにアメリカのGDPに占める比率を減少させたのはEUと日本である。それぞれ四分の一と一割。
次いで、2025年には劇的な変化が訪れる。中国である。2割弱を占めるようになった。ちなみに、日本は半減以下であり、EUも同様である。
私には、ウクライナでの戦いが始まる際、当時のバイデン大統領が米軍を直接関与させるつもりはないと宣言したことは、今のトランプ大統領のウクライナ政策と根を同じにしていて、要するに、第二次世界大戦のときヨーロッパを支えたアメリカはもうどこにもいないということの言い換えなのだと見える。それは、オバマ氏が大統領当時、もはやアメリカは世界の警察官ではない、と言ったこととも文脈が一致している。どちらも民主党である。アメリカはもう昔のアメリカではない、豊かなアメリカではない、という客観的事実がその前提にある。
こうした歴史の経緯を踏まえないでいると、トランプ関税を見誤る。
私はトランプ大統領の狙いは中国にあると見ている。たぶん成功するだろう。
しかし、我々にとっての問題は日本である。
もはや以前の豊さのなくなった選挙民の投票で生まれたトランプ政権は、どこの国が相手であってももはやgreatでなくなったアメリカを再びgreatにするためには手段を択ばないだろう。
問題は一つ。
もはやアメリカをgreatに取り戻すには遅過ぎるか否かである。
遅過ぎるという結論は、万策尽きたときにしか出てこない。したがって、中国はもちろん日本にとっても国難である。500兆円に近い日本の対外純資産が吸い取られるまで、あるいはそれ以上になるまで、Make America Great Againの試みは続くだろう。
中国は軍事的にアメリカに対抗する力を持っている。しかし、日本にはない。それが1985年が第二の敗戦となった理由であった。すると、あるいは中国にとって以上に日本にとっては過酷な国難になるのだと言うべきなのかもしれない。
第二次世界大戦後にできあがった、アメリカ中心の世界の仕組みの組み換えなのである。
必ずや日本社会の仕組みを根底から変えないではいないようにみえる。
おそらく、ユーラシア大陸を支配したモンゴル帝国が力を失い始めたときにも同じことが起きたにちがいない。私は基準通貨についての勉強を改めて始めたところである。
日本はどうすれば良いのか?
少なくとも、日本の側では、安倍さんのサイトに載せていただいた『団塊の世代の物語』のなかで引用した『戦艦大和の最期』における臼淵磐大尉の言葉、日本は「私的な潔癖や徳義にこだわって、本当の進歩を忘れていた。」こと、これがすべての出発点だと私は思っている。
であればこそ、私は未来に対して楽観的な志を持ちうるのである。
トップ写真)トランプ米大統領、中国を訪問 (北京、中国 – 2017年11月9日)
出典)Thomas Peter – Pool/Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
牛島信弁護士
1949年:宮崎県生まれ東京大学法学部卒業後、検事(東京地方検察庁他)を経て 弁護士(都内渉外法律事務所にて外資関係を中心とするビジネス・ロー業務に従事) 1985年~:牛島法律事務所開設 2002年9月:牛島総合法律事務所に名称変更、現在、同事務所代表弁護士、弁護士・外国弁護士56名(内2名が外国弁護士)
〈専門分野〉企業合併・買収、親子上場の解消、少数株主(非上場会社を含む)一般企業法務、会社・代表訴訟、ガバナンス(企業統治)、コンプライアンス、保険、知的財産関係等。
牛島総合法律事務所 URL: https://www.ushijima-law.gr.jp/
「少数株主」 https://www.gentosha.co.jp/book/b12134.html
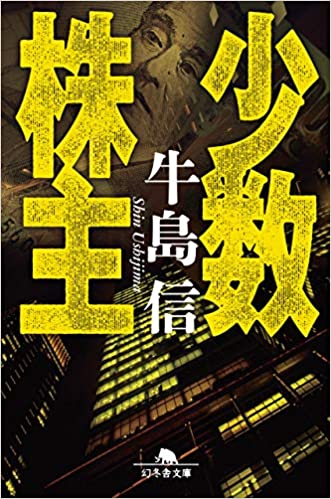

 執筆記事一覧
執筆記事一覧