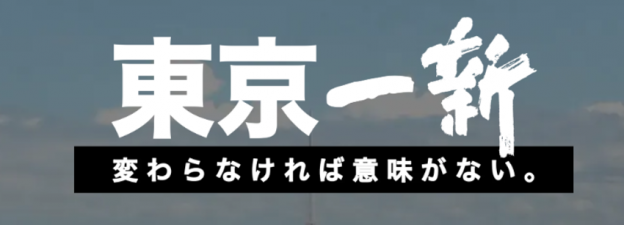【都議選公約分析】④維新の会

西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)
【まとめ】
・東京維新の会は「減税」と「自己決定権」を軸に、行政改革や経済活性化を掲げた具体策を提示。
・行政の効率化やイノベーション推進に優れた提案がある一方で、政策の実効性や対象の妥当性に課題も。
・東京一極集中の是正や都市のグランドデザインには踏み込みが弱く、政党の本来の強みが活かしきれていない印象。
【出典】維新の会HP「維新八策2025」
「東京維新の会は、減税を実現する取組、あなたの自己決定権を高める戦いを始めます。」と主張、「自己決定権」という明確な価値観を新たに定義してきた。第四回は日本維新の会。「見過ごされてきた「おかしい」に、しがらみなく踏み込む。改革政党、東京維新の会。東京の政治や行政には、誰もが「おかしい」と思いながら、空気や利権、前例主義によって置き去りにされてきたことが、たくさんあります。」という問題意識をもとに、個人都民税50%減税、子育て住宅の税制優遇などを提案している。
◆減税と行革
今回は、第一に、減税を中心に打ち出してきているのが特徴だ。年間 6,225 億円の減税により、一人あたり平均 7.7 万円、毎月約 6,400 円が都民の財布に戻るらしい。
 【出典】維新八策
【出典】維新八策
個人都民税が増加して家計を圧迫していることを数字で示し、減税の目的も
①家計の消費を増やすことによる東京の経済成長
②都税収入を抑制することによる行財政改革の推進
③東京の住宅コスト高騰に対する東京に暮らし続ける
と説明。
特に①。名古屋市での事例を出して、「税金を役所が抱え込むより、あなたの財布に戻し、あなた自身の判断で使う方が経済を活性化させるのです。」と減税の意味を説得的に語っている。
第二に、行政改革の視点が貫いている。「行政が一度集めてから再び配る——この過程で膨大な無駄が生まれている」という認識のもとで、
・トランプ政権の政府効率化省を参考にした「東京版DOGE構想」を新設し、全事業をゼロベースで見直す
・不要な事業は廃止し、必要な事業だけに予算を集中させることで、行政のスリム化と都民サービスの向上を両立させる
・ 「都の情報は都民のもの」という原則を庁内に徹底し、黒塗りだらけの「のり弁」から完全公開の「日の丸弁当」を目指し、情報公開が習慣的に行われる仕組みを導入
・知事の公務日程と公用車の運行履歴についても翌日以降速やかに公開
・都民が行政の無駄を指摘できるプラットフォームや「行政サービスの改善提案制度」を創設し、都民の意見を都政に反映
などなどを提案する。「事業ごとに成果指標を設定し、費用対効果を明確化する事業評価制度を強化し、効果の低い事業の見直しや廃止を進めます。」とあり、三重県で始まり全国の自治体で普及・定着した行政評価の必要性や機能についてもしっかりと理解している。だからこそ、具体的な事業見直しが可能になっているのだ。
今回、維新は、一部の高齢者に限定的な恩恵を与えるシルバーパス制度の廃止、外国人患者への医療提供体制の適正化などを訴えている。後者は、都内医療機関における医療費未払いの実態調査をすること、そして外国人観光客の海外旅行保険加入促進と未払い防止策など具体的な費用削減策を明確にしている。
そのほか、老朽化した都営住宅の一部を計画的に民間に売却することについても提案している。他党が「あれもやります!」「これもやります!」という提案が多い中、その点は評価したい。
第三に、産業政策もビジネスの視点を反映した、未来を先取りしたイノベーティブな政策が多いことだ。
・都内の空き家問題と住宅不足の同時解決のため、約90万戸の空き家・空き室を市場で流通させる規制緩和と民間事業者のリノベーション支援を行い、転勤族・単身赴任者・学生から観光客・ビジネス出張者の短期滞在まで、多様なライフスタイルと居住ニーズに対応した住宅として有効活用
・都心区に限定せず多摩地域や島嶼部を含む都内全域の都立公園にドッグランを整備・推進し、ペットと共生する都市環境を実現します。
・自動運転技術の確立に向け、都内での実証実験を積極的に後押しし、技術開発と社会受容性の向上を図ります。次世代モビリティやライドシェアの導入を促進し、誰もが自由に移動できる環境を整備します。
・規制緩和により、新しい多様なモビリティで免許返納後の高齢者や妊産婦、障害者等の移動支援を行い、誰もが外出しやすい環境を整えます。移動の自由を確保することで社会参加を促進し、活力ある共同体を維持します。
・ 「トーキョー・シャンゼリゼ計画」を策定し、銀座や表参道などのウォーカブル化を推進します。駅まちづくりと15分生活圏の確立により、歩いて暮らせる都市空間を創出し、都市の魅力と活力を高めます。
・物流のDX化を最優先に進め、FAXや紙の帳票に依存したアナログな仕組みを刷新します。荷役業務の効率化を図り、デジタル化による生産性向上と国際競争力の強化を実現します。
イノベーションを促す政策としては相対的に質量ともに優れている。
◆そこを支援する必要がどこまであるのか?
公共政策の専門家としていくつか問題提起しよう。
「企業や自治体のテレワーク推進と事業継続計画の策定を促進し、必要最低限の人員でも業務が継続できる体制を構築します。」とあるが、またしても計画だ。行政が計画を作ることが目的になってしまい、計画の運用や成果を残すことが課題なのに、相変わらず計画策定を求めるのはなぜか?
「市場原理を活かした民間事業者によるシェアサイクル運営を支援し、地域交通の多様化を図ります。駅を拠点とした短距離移動の効率化により、生活者中心の回遊性の高い都市空間を創出します。」と言うが、都会の狭いところで危険運転をしているシェアサイクル事業をどう評価するのか?
先ほどの事業評価の手法で、現状を確認、目的と上位目的を設定、成果指標を設定し、リソース(職員の業務時間、コスト)を考えつつ、目標値を検討し、設定。その後、実態をウオッチしつつ、多面的に意見を聞く、目標達成度を評価し、振り返ってみてみることをお勧めする。
また、「区部と西多摩地域、区部と島嶼部など都内の二拠点居住を推進し、二拠点居住にかかる行政手続きの簡略化や拠点ごとの按分納税、オンライン投票など都にできる便宜を図ります。」とあるが、そうした業務を行政が推進する意味が分からない。二拠点居住をできる人たちがやりたい人たちが勝手にやればいい話である。自己決定権という価値観に矛盾するように思える。
◆東京一極集中問題解決はどこに?
最後に、一極集中問題への視点は思ったほど感じられない。国政政党として、維新だからこそ、できる政策提言はあったのではないか。これまで、大阪副首都など、東京一極集中問題解決において一番期待できる政党だったはずだ。オーバーツーリズム、解消されない通勤時の混雑、過剰な都市開発。グランドデザインできるのは行政だけ。都市の開発に規制をかけ、持続的にまちづくりをできる主体は行政なのだ。混雑する東京に辟易としている都民に訴えかける別のやり方があったのではないだろうか。残念でならない。
情勢調査を見ても、新興勢力が伸びている中、非常に厳しい状況である。論理的かつ合理的な政策が特徴で、大阪での実績を持っているがどれだけ都民に訴求するか。日本維新の会に期待する。
トップ写真:Yagi Studio by gettyimages