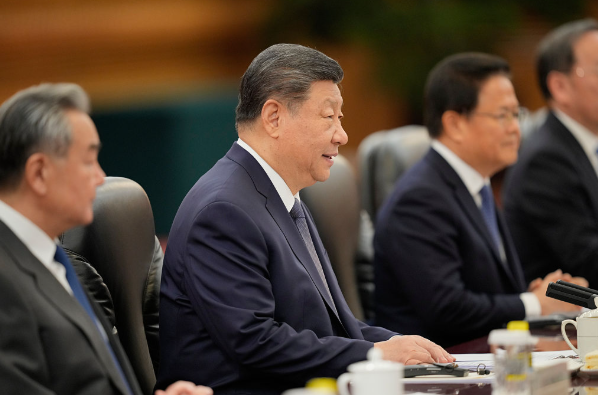名画で知るベトナム戦争の教訓

古森義久(ジャーナリスト・麗澤大学特別教授)
「古森義久の内外透視 」
【まとめ】
・ベトナム戦争の名画『ディア・ハンター』を40年ぶりに観た。
・新生ベトナムの宿敵アメリカへの接近は歴史の皮肉。
・トランプ大統領の「アメリカ第一主義」が支持される理由がわかった。
【注:この記事には複数の写真が含まれています。サイトによっては全て表示されないことがあります。その場合はJapan In-depthのサイトhttps://japan-indepth.jp/?p=43337でお読みください。】
ベトナム戦争の名画とされたアメリカ映画『ディア・ハンター』を40年ぶりに東京で再度、観た。私自身の新聞記者としてのベトナム戦争報道を想い、その後のベトナムやアメリカの現実を重ね合わせて、いままた観た映画からは、いくつもの屈折した歴史の教訓を感じさせられた。
『ディア・ハンター』とはいまからちょうど40年前の1978年に公開されたアメリカ映画である。主題はベトナム戦争だった。タイトルの意味は文字通りの「鹿の狩人」である。実際に鹿狩りが盛んなアメリカのペンシルベニア州の山岳地域の小さな鉄鋼の町が最初で最後の舞台だった。主舞台はやはりベトナムである。
映画は1960年代後半、この町の若者3人が徴兵されて、ベトナム戦争に送られ、米軍兵士として数奇の運命をたどり、1970年代なかばにいたる、という物語だった。
ベトナム戦争が終わったのが1975年4月、挫折を味わったアメリカでは「ベトナム後遺症」が語られた。そのころに制作された初期のベトナム戦争映画の『ディア・ハンター』はアメリカにとっての苦悩や屈辱や悲劇を描き、大ヒットした。アカデミー賞をも獲得した。私はワシントンで観て、自分自身にも長いベトナム戦争報道体験があったために、衝撃や感動を受けたものだった。

▲写真 SA-2ランチャーの前にいる北ベトナム兵士 1960年代 出典:National Museum of the US Air Force
そんな映画がいまや東京で再上映されるとあって、この12月16日、有楽町の劇場でふたたび観賞したのだった。映画のストーリーは次のようだった。
山あいの鉄鋼の町で育ったロシア系移民の子のマイケル(俳優はロバート・デ・ニーロ)、ニック(クリストファー・ウォーケン)、スティーブ(ジョン・サヴェージ)の3人は親友同士で、ともに鹿狩りをする仲だった。3人ともベトナムで戦うことになる。
南ベトナムの山地での激戦の末に3人は北ベトナム軍(革命勢力)の捕虜となり、その敵の将校のロシアン・ルーレットの道具にされる。ロシアン・ルーレットとはもちろんピストルの1発だけ弾丸をこめ、弾倉をくるくる回して、引き金を引く、という危険なゲームである。映画では北ベトナム軍将兵が捕虜の米兵や南ベトナム政府軍将兵にこのゲームをやらせて、自分たちはカネを賭けて楽しむという残酷な設定となっていた。
だがマイケルたちはこのゲームでうまく北軍将兵を撃ち殺して、脱出する。やがて故郷に帰ったマイケルはスティーブが戦闘で両足を失い、帰還して療養中であることを知る。一方、行方不明となったニックがどうも南ベトナムの首都サイゴン(いまのホーチミン市)にいるらしいことを知ったマイケルは救出に向かう。
そのころ南ベトナムでは米軍が撤退し、北ベトナム軍が大軍事攻勢を打ち上げ、南政府を崩壊へと追い込んでいた。陥落が迫ったサイゴンではニックが中国系ベトナム人のギャングに麻薬中毒となって捕らわれ、ロシアン・ルーレットをさせられていた。やっとそんなニックをみつけたマイケルは必死で救出を図るが、彼の目の前でニックは自分の頭を撃ちぬいて死んでしまった。ニックの遺体は故郷の町で運ばれ、婚約者のリンダ(メリル・ストリープ)らに悼まれて葬られる。
マイケルは町の旧友たちとまた鹿狩りに出るが、かつては巨大な鹿をためらいなく仕留めたのに、こんどは獲物を目前にみながら、あえて殺さず、わざと逃がしてしまう。
以上のようなストーリーだった。出演するロバート・デ・ニーロやメリル・ストリープらは後に大スターとなっていくが、この映画はいわばその登竜門だった。そうした男優女優がすごい魅力を発揮したのだ。合わせて背景にベトナム戦争が迫真に描かれていた。戦闘場面や拷問場面はまさに息をのむ迫力だった。
さて私は戦時の南ベトナムで4年近くも過ごし、とくにサイゴン陥落というベトナム戦争の歴史的な終わりの場面を一部始終、渦中にあって、一部始終、目撃した。戦闘の前線にも何度も身を運んだ。『ディア・ハンター』の主舞台を実体験したわけだ。その全体験は『ベトナム報道1300日』(筑摩書房刊、後に講談社文庫)という本にまとめて書いた。

▲写真 『ベトナム報道1300日』古森義久著(講談社文庫)
そんな体験を基にしながらも最初に『ディア・ハンター』を当時の新たな勤務地のワシントンで観たときは、ただただ映画の勢いに圧倒された。劇中の登場男女の魅力に引き込まれ、ストーリーの展開に吸い込まれた。
しかしいままた40年をも経て、同じ映画を観ると、反応はだいぶ異なってくる。余裕と距離感があるせいか、長い年月の経過のせいか、映画は映画としてシニカルに構えるためか。結果としては今回の観賞では映画を越えて、ベトナム戦争やアメリカ人、ベトナム人、さらにはいまのアメリカ・ベトナム両国関係というところまで考えてしまった。
教訓のように感じたのは次のような諸点だった。
まず第一はこの映画はベトナム戦争に関して、それぞれの当事者の最も醜い部分、弱い部分を描いていると思われる点だった。アメリカ帝国主義と戦って勝ったとされるベトナム革命勢力、共産勢力はその将兵が捕虜をロシアン・ルーレットという残酷なゲームの材料にする。民族解放の闘士たちも実は残虐な加害者だった、というわけだ。
南ベトナム政府の軍人たちも民衆を弾圧し、搾取する様子が描かれる。フランス人ビジネスマンも戦争の当事者の両方から漁夫の利を得る腐敗分子となっている。アメリカについても映画の主人公たちのような質朴な青年たちに国家がひどい犠牲を強いるという失態が強調されていた。
第二はベトナム戦争のむなしい部分がことさらに強調される点だった。ただしベトナム戦争は革命勢力からみれば民族独立と共産主義革命のための歴史的な大勝利だった。だが共産主義には同調しなかった南ベトナムの政府や国民にとっては完全な敗北だった。アメリカにとっては大挫折である。
ところが大勝利を飾り、全ベトナム人を外国勢力の支配から解放したという新生ベトナムから肝心の人民たちが大量に国外へと逃げ出すようになった。全土を統一した北ベトナムはベトナム社会主義共和国という名称の国家となったが、その後の20年にもわたり共産主義支配を嫌って国外に脱出する一般ベトナム人が数百万という数にも達した。

▲写真 ベトナムから脱出した難民(ボートピープル)出典:U.S.National Archive
第三には、新生ベトナムは宿敵としたアメリカに接近し、その支援を求めるようになった点である。なんのための対米闘争だったのかとも思わせる歴史の皮肉な展開だった。
ベトナム社会主義共和国はあれほど憎い敵だったはずのアメリカとの国交樹立を切望するにいたった。経済的にもアメリカとのきずなを求めた。中国と敵対した新生ベトナムは軍事的にもアメリカの支援を求めるのだった。アメリカとこれほどに一体になりたいのだったら、なぜあれほど激しく米軍と戦ったのか、といぶかるほどの対米接近だったのだ。
第四には、それでもなおアメリカはアメリカ国民にとっては愛すべき偉大な国家として描かれている点だった。
最終場面はニックの葬儀とその後の親族や友人たちの会食だが、彼らはそこでごく自然にアメリカの愛国歌とされる『ゴッド・ブレス・アメリカ(神よ、アメリカを祝福し給え)』を唄うのだった。
やはりアメリカ人は自国がどんな苦痛にあっても、錯誤をおかしても、国を愛し、神にその祝福を祈る、というわけだ。この場面はいまのアメリカでトランプ大統領の「アメリカ第一主義」がなぜ支持されるのかを説明しているとも感じさせられるのだった。こんなところが私の『ディア・ハンター』再鑑賞の感想だった。
トップ写真:ベトコンに白リン弾を投下する米軍 1966年 出典:National Musium of the US Air Force
あわせて読みたい
この記事を書いた人
古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授
産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧