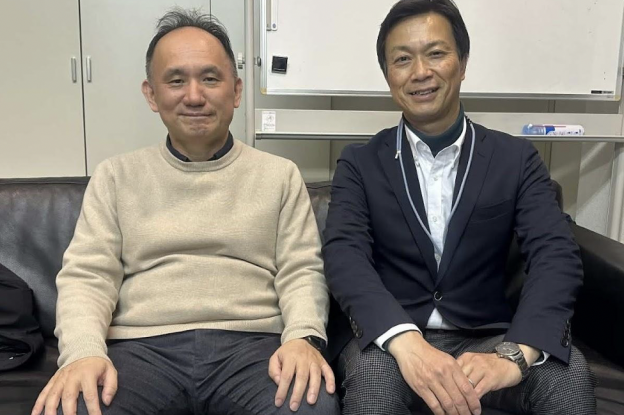東京コロナ診療目詰まりの原因

上昌広(医療ガバナンス研究所 理事長)
「上昌広と福島県浜通り便り」
【まとめ】
・コロナ感染軽快患者の転院先が見つからない。東京は深刻。
・東京は病床少ない。大病院は多いが、400床未満の中小病院が不足。
・都心一等地も地方都市も同じ診療報酬。都心部病院は経営難も。
新型コロナウイルス(以下コロナ)の感染が軽快した患者の転院先が見つからない。コロナ診療が目詰まりを起こしている。
深刻なのは東京だ。1月26日、毎日新聞は、『新型コロナ回復患者、転院先「難民」に 院内感染懸念で断られ』という記事を掲載し、東京大医学部附属病院の岡本耕医師の「新型コロナの退院基準を満たしても、なかなか受け入れる病院が見つからない」というコメントを紹介した。東大病院は重症8床、中等症等30床を運用しているが、状態が改善した患者を転院させられないため、新規入院患者を断わることが多いという。
重症のコロナ患者は兎も角、回復期なら中小病院でも対応できるはずだ。医療機関が多い東京で、なぜ、こんなことになるのだろう。
それは、そもそも東京には病床が少なく、特に中小病院の病床が不足しているからだ。表1をご覧いただきたい。東京の人口1,000人あたりの一般病床数(精神病床は除く)を示している。東京の病床数は5.8床で、全国平均(7.0床)以下だ。さらに格差が著しい。23区に限れば、もっとも多い千代田区(35.3床)と最小の練馬区(1.8床)では約20倍の差がある。

東京の医療機関の特徴は大病院が多いことだ。400床以上の医療機関(以後、大病院と呼ぶ)が運営する病症数は3万5,521床で、全病床(8万296床)の44%を占める。これは全国平均(34%)を大きく上回る。
東京には13の医学部があり、虎の門病院や聖路加国際病院、国立国際医療研究センターなどの有名病院が多い。大病院のウェイトが高くなることは想像に難くない。
問題は、コロナの回復期などを診療する400床未満の病院(以下、中小病院とする)が足りないことだ。このような病院は、怪我や胃腸炎などの「ちょっとした病気」で、紹介状なしで受診することができる。手術を受けるために遠方から受診する大病院と違い、患者の多くは地元住民で、地域に欠かせないインフラだ。
東京での、このような中小病院の病床数は4万4,775床で、人口1,000人あたり3.3床だ。これは全国平均(4.6床)の7割程度だ。
大病院と同じく、中小病院の不足も地域差が著しい。23区内で人口1,000人あたりの病床数が多いのは千代田区(19.7床)、港区(5.6床)、墨田区、北区(何れも5.4床)だ。一方、少ないのは、中央区(0.0床)、文京区(0.9床)、練馬区(1.3床)となる。中央区に存在する中小病院は聖カタリナ病院だけで、運営するのは療養病床41床だけだ。この結果、中央区には中小病院が運営する一般病床はない。
実は、事態はもっと深刻だ。前述の数字は中小病院の病床数を過大評価しているからだ。東京が特殊なのは中小病院の全てが一般患者を受け入れている訳ではないことだ。例えば、千代田区についで中小病院の病床数が多い港区の場合、区内に9つの中小病院があるが、このうち3つは大学病院(東京大学医科学研究所附属病院、国際医療福祉大学三田病院、北里大学北里研究所病院)、2つは専門病院(母子愛育会総合母子保健センター愛育病院、心臓血管研究所付属病院)で、一般病院は山王病院、前田病院、高輪病院、古川橋病院の4つだけだ。
富裕層が利用するイメージが強い山王病院や前田病院の病床を含めても、港区でコロナの回復期を受け入れる中小病院の病床数は人口1000人あたりの1.7床しかない。
つまり、東京には大学病院などの大病院や専門病院は多数あっても、一般人が普通の病気になった場合、紹介状なしで受診・入院できるような病院が不足しているのだ。コロナ感染から回復した患者を引き受けるのは、このような病院であり、これこそが、東京におけるコロナ診療の目詰まりの原因だ。
なぜ、こんなことになったのだろうか。それは、東京の歴史や厚労省の政策が関係する。詳細を知りたい方は拙著『病院は東京から破綻する 医師が「ゼロ」になる日』(朝日新聞出版)をお読み頂きたい。

中小病院不足の原因を考える上で、特に重要なのは、厚生労働省による診療報酬の統制だ。診療報酬は中央社会保険医療協議会(中医協)で決められる。この医療の公定価格は全国一律だ。つまり、都心の一等地の病院でも、地方都市でも同じだ。医療では地方ほど儲かり、都心部は経営難になる。診療報酬が抑制されれば、都心部の病院から経営が行き詰まる。
東京の医療崩壊は、いまに始まった話ではない。東京の一般病床は2007年の8万3,271床から2019年は8万923床へと2.8%も減っている。診療報酬が据え置かれたことに加え、厚労省が一般病床から療養病床へ転換したためだが、この間、人口は増加しているため、人口10万人あたりの一般病床数は653床から581床に11.0%も減ってしまった。
事態が深刻なのは中小病院だ。それは、誰も守ってくれないからだ。開業医のバックには日本医師会が存在するし、大病院の多くは国公立病院だ。赤字でも税金で補填される。大企業や総合大学などが経営する病院も同様だ。2018年1月には名門三井記念病院が債務超過に陥ったことが報じられたが、三井グループが支えた。
中小病院は、そうはいかない。生き延びるためには、収益を上げねばならず、そのためには、専門分野に特化するか、不採算部門を切り捨てるしかない。医療法人社団大坪会は、2007年4月に文京区大塚の日通病院を買収し、小石川東京病院と名称を変更したが、2017年4月に診療を停止している。このケースなど、その典型例だ。
現在、文京区には東大病院など4つの大学病院本院や都立駒込病院があるが、急性期の一般病床を運営する中小病院は大坪会が経営する東都文教病院だけだ。冒頭にご紹介した東大病院の医師が、コロナ患者の転院先を確保するのに困るのも当然だ。

コロナ診療の目詰まりは、東京の医療の脆弱性を象徴している。東京の高齢化は待ったなしだ。特に中心部で、その傾向が顕著だ。港区の場合、2015年に2万387人だった75才以上の人口は、2030年には3万549人へと50%も増加する。東京の医療提供体制は、このような社会の構造変化に対応しなければならない。
高齢化と共に必要とされる医療は変わる。大学病院や専門病院が得意とする高度医療ではなく、慢性疾患のケアや介護の占めるウェイトが高くなる。胃腸炎による脱水などで入院が必要になることも増えるだろう。そんなときは近くの病院に入院したい。ところが、東京には大学病院・専門病院とクリニックは多数あるものの、このような患者を引き受ける中小病院が不足している。
一方、団塊世代が高齢化すれば、外科手術などの侵襲的な治療の需要は低下する。大学病院を中心とした高度医療提供体制は過剰となる。このような医療に従事する医師や病床を、如何にして高齢者が必要とする医療に転換するか、コロナ対応は、今後の東京の医療のあり方を問う試金石である。
トップ写真:コロナ患者の病床(イメージ) 出典:Gabriel Kuchta/Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
上昌広医療ガバナンス研究所 理事長
1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧