【都議選公約分析】②国民民主党

西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)
【まとめ】
・国民民主党の公約は、手取り増加を目指す減税や住宅・介護・教育支援を中心に、多様な政策課題に対応しており、中道・若者層に訴求している。
・一方、インターナショナルスクール誘致など一部政策には行政の関与に疑問が残る。
・政策の網羅性はあるが、行政が関与すべき範囲が不明瞭で、東京一極集中問題など都市全体のグランドデザインに対する視点は欠けている。
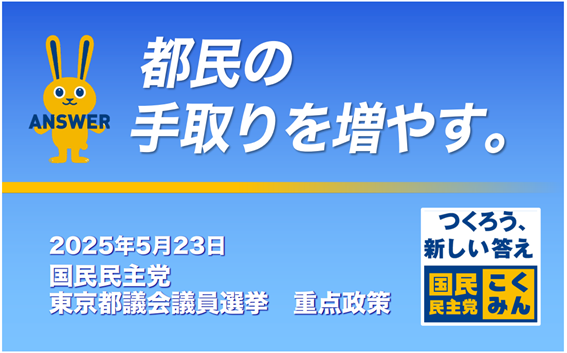
【出典】国民民主党、重点政策
手取りを増やす!都議選公約分析、第二回目は国民民主党としたい。
国民民主党は、住宅価格・家賃高騰を踏まえた住宅購入支援や住居費負担軽減、固定資産税の減税による家計負担軽減、就職氷河期課題への対応(都職員としての正規雇用、就労支援、住宅支援等)、無電柱化、教職員の働き方改革・個別最適学習実現に向けた教育 DX の推進、都立学校のグローバル化、不登校支援等による多様な才能と学びを支える教育環境の整備などの「重点政策」が並ぶ。中道層の都民の心に打つSNSの活用で成功を収めつつある政党。そのターゲットとみられる若者や中道層に響く内容になっている。
都内に在住する0歳から18歳までの子どもを対象に、所得制限を設けず一人当たり月額5,000円を支給する「018サポート」の月1万増、中小企業への固定資産税の軽減措置拡充などである。
◆さすがの問題提起
さて、手取りを増やすための減税について考えてみたい。全世界の減税政策の考え方の基底には、税収が増えると必要以上に事業を作ったり、仕事を作ったり、補助金を配布したりしてお金を使う、そして、それが定常化し、結果、組織としても肥大化する。だから、そもそもの税金額を減らす(減税)ことが必要だという問題意識がある。
国民民主党はそういった文脈で言っているようには見えないこともあるが、行政改革の面でもなかなか言わないことを言っている。今回、「不断の行財政改革」として外郭団体の精査を主張してきた。
「現在東京都では33団体の外郭団体があり、内訳は公益財団法人が20団体、一般財団法人が2団体、社会福祉法人が1団体、特別法人が1団体、株式会社が9団体となっています。これらの外郭団体の経営についてチェックを強化し、民間活力を活用して代替可能なものの精査を行い、行政の効率化を図ります。また、外郭団体が事業実施することで税金の無駄遣いが見えにくくなっているおそれがあることから、外郭団体が行う事業についても精査を行います。」(「国民民主党 東京都議会議員選挙2025 公約 2025年5月23日発表 国民民主党東京都総支部連合会」)と説明する。
東京都は余裕があるため、都民のニーズにこたえていくうちに、どんどん業務を拡大していき、結果、民間企業でもできるような事業も、事務事業評価をしていなく必要性が疑問な事業も多く存在する。その受益者である都民は安くサービスを受けられることもあり、恩恵も多い。他方、民業圧迫面もあるといってもよい。この点を切り込むのはさすがである。
また、介護などについてもいろいろと細かく「課題」を提起している。
・介護福祉職の所得倍増計画
・ショートステイや小規模多機能型居宅介護の設置
・ケアプランデータ連携システムの利用促進
・介護施設指定審査と指導を市区町村に権限移譲
「小規模多機能型居宅介護」など、必要性が高いが、あまり知られていない政策を打ち出していく。そこはさすがだ。グランドデザインは明らかにされていないが、こうした問題意識を持っていることは評価したい。
◆そこを支援する必要がどこまであるのか?
専門家として2つの視点を問題提起しよう。
第一に、インターナショナルスクールの誘致という政策である。「子どもたちの能力を伸ばす教育の推進教育の多様性とグローバルな視点を育むため、国と連携しながらインターナショナルスクールの誘致を積極的に推進します。すべての子どもたちに、親の経済状況や家庭環境にかかわらず、多様な選択肢と質の高い学びの機会を保障し、教育の機会均等を実現する東京を目指します。」(「国民民主党 東京都議会議員選挙2025 公約 2025年5月23日発表 国民民主党東京都総支部連合会」)というが、教育産業が日本にニーズがあるなら進出すればいいだけの話である。誘致活動の業務を都庁の行政職員はさせられるわけだ。その部分への行政関与は疑問である。そもそも公教育をしっかり実施することが優先度が高くあり、過剰な有権者へのおもねりとしか見えない。党関係者や有力者の中に、教育に問題意識の高いエリートのご家庭や利害関係者でもいるのだろうかと推察してしまう。
また、「国民民主党 東京都議会議員選挙2025 公約 2025年5月23日発表 国民民主党東京都総支部連合会」には、資料の最終ページに「参考 上記以外の個別の政策課題一覧」として数多くの「課題」が書かれている。
・闇バイトなど加担者を減らし特殊詐欺の防止
・東京都の女性管理職比率を30%まであげる
・DV被害者支援、DV加害者更生プログラムの推進・支援拡充
・主権者教育の拡充
・育児・介護のダブルケアラー、ヤングケアラーへの支援
など「政策課題」としては非常に良いものも並ぶ。
しかし、
・スタートアップ企業に認証制度導入
・製造業の設備更新助成拡充
・自転車専用レーンの設置拡充
・企業の女性管理職比率を上げるために周知啓発強化
・可処分時間の確保・増加の推進
・東京の「食文化」の魅力の発信
・桜や紅葉の名所のライトアップ推進
・アーツカウンシル東京の機能強化
・文化芸術政策に対する職員の意識啓発
あれもこれも・・・のオンパレードである。必要だけど、行政がやることか?問題解決には他の方法があるのでは?行政ですでにやっていることを再度言語化しただけでは?と疑問を感じることが多い。他の政党ともあまり変わらない。具体策を提起するとよりよかったのかもしれない。
◆東京一極集中問題
最後に、一極集中問題への視点は全く感じられない。オーバーツーリズムについては、「地域住民の生活環境を守り、住民と観光客が快適に過ごすことのできる環境を維持するための対策が必要です。」と主張し、宿泊税の増額を打ち出してはいる。しかし、国政政党として、東京一極集中問題への対処方法を視野に入れたものはない。解消されない通勤時の混雑、過剰な都市開発。グランドデザインできるのは行政だけ。都市の開発に規制をかけ、持続的にまちづくりをできる主体は行政なのだ。災害対策も含めて考えてもらいたい。
選挙情勢では、選挙ドットコムの調査によると現在都議会に議席を持っていないのにもかかわらず、躍進が想定されている。山尾さんの件で支持率が落ちたりしたが、少しは議席を獲得するだろう。国民民主党に期待する。
トップ写真)スーパーでのショッピング
出典)Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
西村健人材育成コンサルタント/未来学者
経営コンサルタント/政策アナリスト/社会起業家
NPO法人日本公共利益研究所(JIPII:ジピー)代表、株式会社ターンアラウンド研究所代表取締役社長。
慶應義塾大学院修了後、アクセンチュア株式会社入社。その後、株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)にて地方自治体の行財政改革、行政評価や人事評価の導入・運用、業務改善を支援。独立後、企業の組織改革、人的資本、人事評価、SDGs、新規事業企画の支援を進めている。
専門は、公共政策、人事評価やリーダーシップ、SDGs。












 執筆記事一覧
執筆記事一覧




















