【都議選公約分析】①れいわ新選組

西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)
【まとめ】
・れいわ新選組は、積極財政と再分配を軸に「大きな政府」志向の政策を打ち出している。
・特に大企業への課税強化や国民健康保険料の引き下げなど、経済的弱者への支援を重視。
・一方、公営住宅の大規模増設や非正規公務員の正規化には、空き家問題や行政の効率性などの観点から疑問も。
これから東京都議選公約分析を行っていきたいと思う。第1回目は、若者の人気が高まり、存在感を増している「れいわ新選組」。SNSを駆使し、山本太郎さんの対話を進める姿勢で、じわじわ人気を得ている。今回の東京都議選は何を主張しているのか、その公約を見てみよう。基本的なメッセージは、「あなたの生活が苦しいのはなぜでしょう」という問いかけから始まり、積極財政と都民の生活を支える給付金、公営住宅を50万戸などの提案を掲げている。
◆既存都政の政策と特徴
特に、「財源はある」という問題提起は一貫している。財源はあるから、お金を再配分せよ!ということである。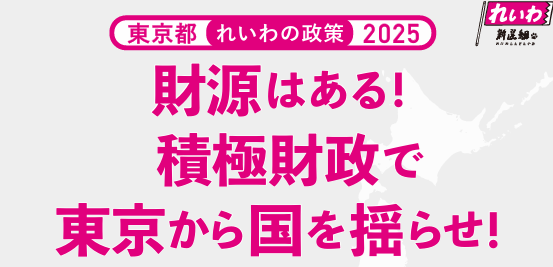
【出典】HP
具体的な中身を見てみよう
◯東京都の税収は4年連続増収で約7兆円に達しています。さらに基金も全体で1.6兆円あります。東京都の豊かな財政を一律・公平な給付金などインフレ対策に活用し、※「れいわ緊急政策」とともに人々の生活を支えます
◯国民健康保険料を引き下げ、国民負担を減らし、使えるお金を増やします
物価高騰対策、つまり、経済的弱者を支えるという哲学が一貫していている。高騰する物価や家賃で苦しむ都民負担を減らそうということだ。
◯都内の老朽化した道路、橋、トンネル、水道管などさまざまな社会インフラの改善・修繕・更新を行います
◯非正規公務員を正規化します。非正規公務員は女性が大半で、福祉や教育の現場を担っています。移行までは給与を大幅引き上げます
また、社会的な基盤となるインフラ整備、必要な人への公的サービスを増やすこと、行政機関を分厚くする政策が掲げられている。「大きな政府」への志向が強く、明確にみられる。
◆画期的な問題意識
画期的な政策提案も多い。
◯資本金1億円以上など超大手企業の法人都民税・法人事業税の引き上げ
◯国民健康保険料の引き下げ
◯隠れ教育費
公平性の観点から、かなり再配分色の強い政策を強烈に打ち出してきた。大企業などの強者にはそれなりに払ってもらおうというスタンスである。哲学が体現されているし、言うべきことをいっている。なかなかメディアでは紹介されないし、言われないテーマではある。大企業は景気がいいのにもかかわらず都民は物価高に苦しんでいるというロジックで困窮する都民に訴えかける。
隠れ教育費について解説すると、保護者への様々な費用負担のこと、私費負担ともいう。運動会・文化祭・発表会、校外学習・遠足、修学旅行、部活動、卒業準備など様々な費用のこと。制服、体操着、ジャージ、給食費、水着などが学校の指定品として購入しないといけないし、小学校の入学時にはランドセル。引き出し、道具箱を用意させることもあり、上履き、体育館シューズ、名札、通学帽など、高い値段の指定品を買わざるを得ないのだ。そのあたりに目を付けたのはさすがである。
◆今さら公営住宅?
専門家として2つの視点を問題提起しよう。
「公営住宅を倍の50万戸超に増やします。新しい公営住宅は高い断熱基準を適用して光熱費ゼロ住宅(ZEB/ZEH)とすることで、燃料貧困をなくし、地域経済を活性化させます」と主張する。弱者保護にはとてもいい政策で、安い家賃で公的住宅に住めるというのは非常に助かるだろう。しかし、都内の各自治体の空き家率を知っているのだろうか?空き家率は11%。その人口減少時代に減らしてどうするということだ。公営住宅じゃなくても、住宅はたくさん供給されている。空きアパートもある。そちらへの誘導、家賃補助で十分ではないか。都営住宅は、高度経済成長に東京に来て家のない労働者家庭のために作ったもの。単身者向けでもない。そして、倍増させると、不動産業者には民業圧迫に見えるかもしれない。これだけ空き家が増えているのだから、その対策を先に優先し、わざわざ作ることへの理由がない。東京都近隣の公営住宅においても、ほぼ外国人が住む団地になっているところもある。
第二に、「非正規公務員を正規化」と言う点である。働き方が流動化・多様化していて、副業やスポットワークなど働き方が多様化している。公務員への就職希望者は、全国的に問題になるほど減少している。正規化で人件費が固定化していくし、そもそも適正人数がどれくらいなのかもわからない。これまで高度経済成長期に行政の役割は肥大し、さらに、色々な事業を手掛けている。東京都の仕事は、財政的に余裕がある
からできている業務が多い。そういうものを見直し、事務事業評価を行い、業務プロセスを改善すれば、そんなに公務員を増やすべきなのか?と思うのだ。
◆東京一極集中問題
最後に、一極集中問題への視点は、大規模開発の見直しに明記されてはいる。しかし、東京一極集中問題への対処方法を視野に入れたものにはなっていないのは残念であった。オーバーツーリズム、解消されない通勤時の混雑、過剰な都市開発。グランドデザインできるのは行政だけ。都市の開発に規制をかけ、持続的にまちづくりをできる主体は行政なのだ。災害対策も含めて考えてもらいたい。
選挙情勢では、選挙ドットコムの調査によると現在都議会に議席を持っていないのにもかかわらず、れいわ新選組の躍進が想定されている。投票率があがり、若者が投票所に行けばそれなりに議席を獲得するだろう。れいわ新選組に期待する。
トップ写真)東京2020オリンピック選手村 東京 2020年3月31日
出典)Photo by Carl Court/Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
西村健人材育成コンサルタント/未来学者
経営コンサルタント/政策アナリスト/社会起業家
NPO法人日本公共利益研究所(JIPII:ジピー)代表、株式会社ターンアラウンド研究所代表取締役社長。
慶應義塾大学院修了後、アクセンチュア株式会社入社。その後、株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)にて地方自治体の行財政改革、行政評価や人事評価の導入・運用、業務改善を支援。独立後、企業の組織改革、人的資本、人事評価、SDGs、新規事業企画の支援を進めている。
専門は、公共政策、人事評価やリーダーシップ、SDGs。












 執筆記事一覧
執筆記事一覧




















