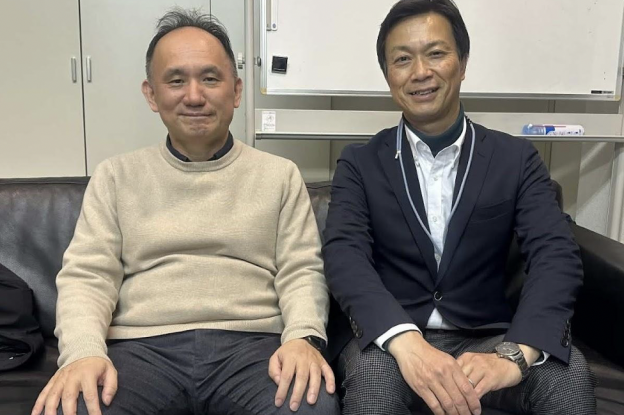若者たちが福島をハブに世界へ飛躍する 坪倉研の使命

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)
「上昌広と福島県浜通り便り」
【まとめ】
・2024年、医師の働き方改革で残業規制が始まり、医師不足は益々悪化する。
・医師育成を考えれば、医局と大学病院を切り離すべき。
・福島県立医科大学坪倉正治研究室の若者たちが、福島をハブに世界へ飛躍することを期待したい。
2023年が暮れようとしている。少子高齢化が進む我が国で社会保障体制の維持は喫緊の課題だ。世間の関心も高く、2023年には全国紙5紙に「医療崩壊」という単語を含む記事は65報も掲載されている(2023/12/18現在)。
問題点の一つが医師不足だ。2024年には医師の働き方改革として、残業規制が始まる。医師の総労働時間は減るわけだから、常識的に考えて、医師不足は益々悪化するだろう。
どうすればいいのか。すぐにできることは医師の適正配置だ。ただ、行政による強制配置には限界がある。自治医科大学設置から医学部受験での地域枠まで、さまざまな対策を採ってきたが事態はあまり改善していない。
我が国に必要なのは、今後、需要が増加する分野に若手医師を誘導し、彼らに成長してもらうことだ。
私が注目するのは、福島県立医科大学の坪倉正治研究室(放射線健康管理学講座)だ。来春、坪倉研から最初の卒業生が出る。川島萌さんだ。
川島さんは、宮城県内の高校を卒業し、2018年に福島医大に入学した。入学後、坪倉研が主宰する「論文愛好会」に加わり、筆頭著者1報、共著者6報の英文論文を発表した。12月11日、朝日新聞が彼女が筆頭著者の論文を『南相馬の「関連死」半数が要介護認定 福島県立医大などの分析』という記事で大きく報じた。ご覧になった方もいらっしゃるだろう。
その後、12月17日には、同紙福島版の「東北人」のコーナーに、「震災経験を乗り越えた人 次の「災害」にいかす」というタイトルで川島さんのインタビュー記事を掲載した。
坪倉研には、現在、MD-PhDコースの学生6人、「論文愛好会」の学生2人が在籍している。彼ら以外にも、東京大学、広島大学、慶應義塾大学や海外の学生も訪れ、共同で臨床研究や論文執筆を進めている。
川島さんは、来春、福島県内の病院で初期臨床研修を始める。そして、今後、坪倉研からは毎年1−2名の学生が巣立つ。彼らをどのように育てるか、今後の若手医師育成を考える上で重要だ。
若手医師は、一人でキャリアを積み上げることはできない。先輩の指導が必要だ。日本の医療界では大学医局が、この役割を果たしてきた。大学医局に入れば、大学を中心に関連病院をローテーションした。この間、初期研修医から部長候補の中堅世代まで、先輩からポストに応じた指導を受ける。
先輩による指導は医師に限った話ではない。弁護士や会計士などの士業も、若手は先輩の指導のもと、仕事を通じてスキルを磨く。このような組織は、通常、パートナー制で運営され、若手はパートナーの部下となる。
大学医局が弁護士や会計士と違うのは、大学病院という直轄の巨大な現業を抱えていることだ。私が懸念するのは、大学病院の生産性が低く、その存在が若手の成長の機会を奪っていることだ。
東大病院の場合、令和3年度の附属病院収益は537億円だ。短時間有期雇用職員を含み1,689人(歯科医、研修医を含む)が働いている。一人あたりの売上は3,179万円にすぎない。
これでは病院経営はやっていけない。赤字を補助金などで穴埋めしてきたが、昨今の財政事情を考えれば、いつまでも続けられない。そうなれば、人件費を抑制しなければならない。
その1つが後期研修医制度だ。東大病院の1年次の後期研修医(専攻研修医)の時給 1807円で、1週間の勤務が31時間内の非常勤雇用だ。
後期研修医は、20代後半から30代前半で、最も働ける時期だ。市中病院に勤務すれば、常勤で年収は1000万円以上、非常勤で時給は1万円以上は稼げる。
この仕組みの問題は、厚労省が後押しする形で、日本内科学会や外科学会の連合体である一般社団法人日本専門医機構が仕切り、実質的に義務化されていることだ。この仕組みを通じ、東大病院は若手医師を安くこき使っていると見なすことも可能だ。ブラック企業といっても決して過言ではない。
これは東大病院に限った話ではない。大学病院の経営は、どこも似たり寄ったりだ。本来、スクラップ・アンド・ビルドしなければ大学病院の体制を温存し、若手医師にブラック労働を強いている。これでは人材は育成されない。ツケを払わされるのは次世代だ。
若手医師を育てるには資金が必要だ。多くの大学病院に、その力はない。どうすればいいのか。医師育成を考えれば、医局と大学病院を切り離すべきだ。原理的には可能だ。大学附属病院は医学生や医師教育に必須ではない。その証左に米国のハーバード大学には附属病院はない。
また、そちらの方が社会の需要に応えることができる。それは、社会情勢の変化とともに、若手医師が修業するに相応しい医療機関も変わりつつあるからだ。高齢化が進むわが国では、従来型の高度医療の需要が減り、プライマリケアの重要性が増している。厚労省の「医療施設調査」によれば、2000年代に入り、年平均5%増加していた手術数が、2017年の調査では2.1%増にペースを緩め、2020年には減少に転じた一方、後期高齢者は激増している。後者の領域に飛び込むことが、医師として成長するための近道だ。
坪倉医師は、このことを身体感覚として知っている。それは、彼が飛躍したきっかけが、東日本大震災直後に福島県浜通りに飛び込んだことだからだ。彼は、被災地という「現場」でプライマリケアを担当し、その結果を数多くの医学論文としてまとめた。
震災当時、彼は私が主宰する東大医科研の研究室の大学院生だった。私が、福島入りを勧めたのは、それが社会の要請に応えることになるからだ。現場での試練は若者を鍛えるし、社会課題に真っ向から取り組む若者には、多くの応援団がつく。
2021年3月、米『サイエンス』誌は、彼の活動を5ページで特集した。地球温暖化が加速し、国際紛争が増加した。災害医療や被曝対策は、世界が注目を集める領域だ。『サイエンス』誌の扱いは、このような時代背景を反映したものだ。
現場から離れ、机上の空論を弄んでいても、このような体験はできない。これは私の原体験に基づく実感だ。私は、1990年〜2000年代にかけて、東京大学や国立がん研究センターなどで医師としてのキャリアを積んだ。その後、ノバルティス降圧剤事件やさまざまな研究不正、さらに科研費不正や贈収賄で責任を追及されることになる先輩医師や、医系技官と共に働いた。
彼らの関心は医療現場より、「実験」や「国策」にあり、お膝元の病院が、時代遅れになりつつあることを問題視しなかった。私には、彼らが誇る「巨大病院」が「戦艦大和」に見えた。
私は、あまりの認識の違いに驚き、なぜ、こうなるのか考えた。行き着いたのは、現場感のなさだ。私が所属した東大第三内科の血液グループの場合、多くの先輩医師は、医学部卒業後、短期間(多くは一年間)の外部病院の研修を終え、東大病院で「実験」していた。また、国立がん研究センターでご一緒した医系技官は卒業後、霞ヶ関に閉じこもっていた。そして、現場ではなく、ずっと彼らにとっての「本部」にいることを誇りに思っていた。
私は、2005年に東大医科研に研究室を立ち上げると、若者に対して、現場で修業するように勧めた。その際に留意したのは、優秀な理事長や病院長の存在、および病院の経営状況だ。全国一律の診療報酬体系を考えれば、都内より地方にこのような理事長・病院長は多い。現在、我々のチームの若手医師が、福島はもちろん、四国や九州の病院で「修業」しているのは、このためだ。
若手が成長するには、様々な環境で働いた方がいい。医療ガバナンス研究所では、若手医師は、私をはじめとしたメンターが仲介する形で、数年おきに勤務先を変える。国内外に留学することもある。
これは、我々のグループが、自前の「大病院」を抱えていないから出来る芸当だし、小規模なグループだからこそ、若手医師の個人的な事情に配慮した対応が可能となる。これが従来型医局との違いだ。このような仕組みは、若手医師を成長させながら、我が国の医師偏在を是正する。
今後、坪倉研も同じような組織体へと発展するだろう。坪倉研の特徴は、福島出身者が多いことだ。災害医療への関心が高まる世界の医学界で、彼らへの期待は大きい。若者たちが、福島をハブに世界へ飛躍することを期待したい。それを演出することこそ、坪倉教授の使命である。
トップ写真:右から二人目が川島さん、三人目が坪倉教授(筆者提供)
あわせて読みたい
この記事を書いた人
上昌広医療ガバナンス研究所 理事長
1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧