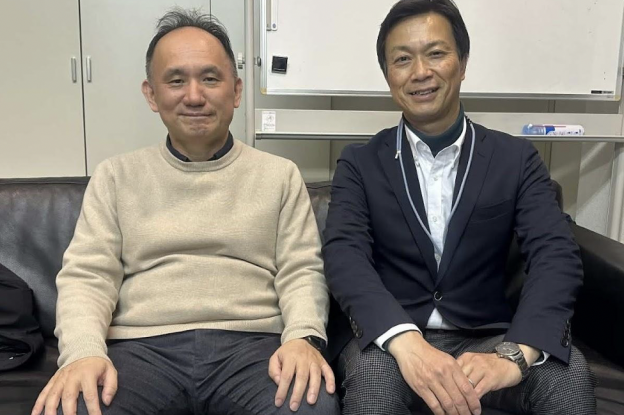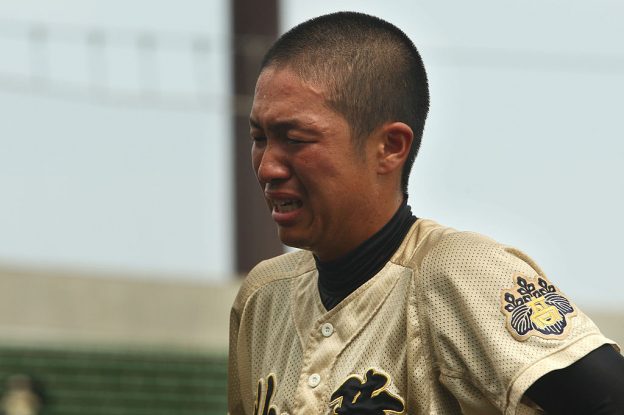福島医大から始まる地域再生――高等教育が育む復興の力」

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)
「上昌弘と福島県浜通り便り」
【まとめ】
・福島医大は震災後の公的支援により急成長し、医療・研究の拠点となった。
・国立医学部がない福島で、地元の優秀な人材を育てる中心的役割を果たす。
・高等教育の充実は、福島の歴史的劣位を克服し地域再生を導く鍵となる。
地域力は、畢竟、人材力だ。特に高等教育を受けた人材は重要だ。前回、福島は、この点で見劣りすることを紹介した。これは明治維新以来の歴史が関係しており、一朝一夕で解決しない。福島にとっての希望は福島県立医科大学(以下、福島医大)の存在だ。本稿でご紹介したい。
まずは、福島の医学教育について説明しよう。特記すべきは国立の医学部がないことだ。これも歴史が影響している。福島以外に国立の医学部がない県を見れば、一目瞭然だ。西から和歌山、奈良、神奈川、埼玉、栃木、福島、岩手だ。すべて徳川家や親藩、譜代大名のお膝元だ。
明治維新は西国雄藩が徳川家を打倒する形で成し遂げられた。内戦に勝利した西国雄藩は藩校を発展させる形で、地元に高等教育機関を誘致した。一方、東国の高等教育機関は閉鎖された。戦前、九州には3つの官立医学部が存在したが、関東、甲信越、東北には合計しても4つしかない。
本来、福島は医学教育の先進地域だった。明治時代、白河医術講議所や、その後継機関である須賀川医学所、さらに福島医学校が存在したが、1887年(明治20年)に廃止され、仙台の第二高等中学校に附設された医学部に吸収された。その後、福島に医学校ができるのは、戦時中の1944年(昭和19年)の福島県立女子医学専門学校設立まで待たねばならなかった。この女子医専が、戦後の学制改革で現在の福島医大となる。
三重大学、岐阜大学など、戦後に県立から国立に移管された医学部もあるが、福島の場合、県立のまま据え置かれた。
福島医大は、長年、低迷する。臨床、研究のいずれにおいても、評価は低かった。ところが、東日本大震災以降、急成長する。それは巨額の公的資金が投入されたからだ。その事業規模は急拡大した。震災前の2008年度の同大学の経常収益は263億円だったが、2023年度には662億円へと2.5倍増加している。この事業規模は、戦前の官立6医科大学を前身にもつ名門総合大学である金沢大学(637億円)や長崎大学(643億円)よりも大きい。
ちなみに、東北大学の経常収益は、2008年の1201億円から、2023年の1513億円へと1.26倍に増えただけだ。福島医大の伸びが、如何に特記すべきものかお分かり頂けるだろう。
2008年から2023年の間に福島医大の経常収益は399億円増えたが、その内訳は、病院収益207億円、運営費交付金63億円、受託事業など収益44億円と続く。これは、この間に福島医大の診療・研究の規模が飛躍的に拡大したことを意味する。
人材育成には時間を要する。当座は外部から医師や研究者を招聘するしかない。長崎大学から副学長として招聘された山下俊一氏など、その典型例だ。このような人材が加わったことで、福島医大の診療や研究レベルは向上した。研究レベルは論文数で客観的な評価が可能だ。
医療ガバナンス研究所は、定期的に国公立大学の臨床研究の生産性を調査している。具体的には、米国立医学図書館データベース(PUBMED)が定義する「コア・クリニカル・ジャーナル」に掲載された臨床論文数を常勤医師数でわった指標を用いて、大学をランキングしている。2009~12年と2016~18年の調査結果の比較を図1に示す。

図1
前者では、50大学中40位だった福島医大は、2016~18年の調査では、京都大学、東京医科歯科大学、名古屋大学に次ぐ4位に躍進した。
では、急成長した福島医大には、どの地域から学生が集まっているのだろうか。表1に今春、同大医学科に合格した学生の出身地を示す。114人の合格者のうち、もっとも多いのは関東地方で54人だ。次いで東北地方が52人で続く。この二つの地方で、合格者の93%を占める。
[caption id="attachment_87516" align="alignnone" width="394"] 表1[/caption]
表1[/caption]
では、具体的にどの地域が多いのだろうか。最も多いのは福島県(38人)で、東京都(17人)、栃木県(12人)、宮城県(11人)と続く。福島医大が福島県の中通りに位置するためだろうか、常磐線沿線ではなく、東北本線・東北新幹線の沿線からの合格者が多い(図2)。
[caption id="attachment_87503" align="alignnone" width="431"] 図2[/caption]
図2[/caption]
図3は、福島医大の18歳人口1万人あたりの合格者数を示している。福島県が圧倒している。このような事実は、福島医大が地元出身の人材を育成していることを意味する。
[caption id="attachment_87526" align="alignnone" width="567"] 図3[/caption]
図3[/caption]
もちろん、このような状況になっていることには、制度的な「追い風」も存在する。福島医大の定員は、東日本大震災後に増員され、現在は130人だ。このうち約45人は、卒業後一定期間を県内で勤務することが義務付けられている地域枠だ。また、地域枠とは別に、50名以下という条件で「学校推薦型選抜(A枠)」での入学者を受け入れている。このような制度は、福島県出身者に有利に働くだろう。
ただ、このような「追い風」があるにせよ、東日本大震災以降、福島県内の優秀な高校生が、福島医大へと進み、一流の医師や研究者と接する機会が増えたことは、福島の復興を考える上で大きい。
米国のシリコンバレーやボストンなど、世界の多くの町は大学を中心に発展した。日本ではつくば市が、その典型だろう。地価は上がり、都心部まで電車が通じた。つくば市以外にも、長崎市、徳島市、広島市、岡山市、神戸市などの地方都市には有力な国立大学が存在し、その卒業生が中心となって町を発展させた。
東日本大震災を経験し、福島医大は規模を拡大し、実力を飛躍的に向上させた。この大学を中心に、福島での人材育成が進むことを願っている。明治維新以来の国家の「冷遇」を挽回する好機である。
写真)福島県立医科大学
出典)福島県立医科大学
あわせて読みたい
この記事を書いた人
上昌広医療ガバナンス研究所 理事長
1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧