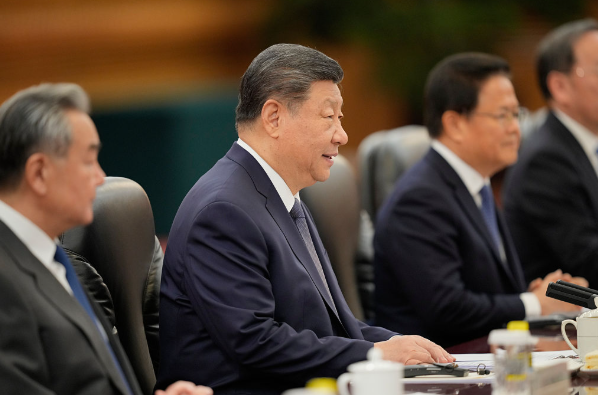ベトナム戦争からの半世紀 その17 北ベトナム軍司令官の驚きと喜び

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)
「古森義久の内外透視」
【まとめ】
・南ベトナム軍の突然の撤退に北ベトナム軍司令官は驚きと喜びを感じた。
・北軍は当初、プレイクとコンツムの制圧に苦戦を予想していた。
・撤退する南軍に対し、北軍はフルスピードでの追撃命令を下した。
南ベトナム軍の中部高原からの一方的な撤退は北ベトナム側にどう映ったのか。その新展開に北軍はどう対応したのか。その実態は北ベトナム人民軍のバン・チエン・ズン参謀総長が戦後すぐに発表した長大な回顧のベトナム戦記で明らかにされた。その内容から要点を報告しよう。
その前にベトナム戦争の終結に決定的な役割を果たしたバン・チエン・ズンという人物に光をあてよう。これまでもズン参謀総長の回顧録などをたびたび引用してきた。だが彼がどんな人物かにはほとんど触れなかった。ズン氏はいうまでもなく戦争中の北ベトナム(ベトナム民主共和国)の人民軍を指揮した歴戦の戦士である。だがベトナム人民軍といえば、世界的にまずボー・グエン・ザップ氏の名があまりに広く知られてきた。
ザップ氏はフランスに対する軍事闘争を指揮し、とくに1954年のフランス軍とのディエンビエンフーでの激戦ではフランス側が堅固に固めた要塞を制圧し、フランス将兵数千人を投降させた。この勝利が80年ものフランスの植民地支配に終止符を打った。
ザップ氏は1930年代にインドシナ共産党(その後のベトナム労働党の前身)に加わり、ホー・チ・ミン主席の軍事面での右腕として抗仏戦争で活躍した。その軍事の才能は国際的にも天才とか鬼才として高く評価された。
ズン氏はそのザップ氏の直属の部下として抗仏戦争で活動してきた。インドシナ共産党への入党は1937年と、まず党での政治活動歴が長い。1946年ごろからのフランス植民地軍との戦いではベトナム北部の各地でゲリラ部隊を指揮して、戦果をあげた。その結果、共産党内で中央委員会の政治局員に選ばれ、一時は国防大臣にも任命された。ベトナム人民軍では1950年代からザップ総司令官の下で参謀総長を務めた。
ズン氏は60年代からのアメリカが直接に軍事介入して以降のベトナム戦争では前線の総指揮官として長年、活動した。1971年春の米軍と南ベトナム軍によるラオス作戦でも北軍の総司令官として戦い、翌72年春の春季大攻勢でも南ベトナム北端のクアンチ省の制圧の指揮官でもあった。そして1975年2月には南ベトナムの中部高原制圧の作戦を任されたのだった。つまりは歴戦に歴戦を重ねてきた軍人であり、75年春には57歳だった。
さてそのズン将軍の戦記から、彼自身が南側の中部高原撤退の動きにどう反応したかを報告しよう。
ズン将軍にとっても南側の中部高原からの撤退は晴天の霹靂だった。まったく予想しなかった出来事だったのだ。前にも述べたようにこの時点での北ベトナム軍の戦略目標はプレイクとコンツムへの包囲網を強固にして、時間をかけて、この両省都を制圧することだった。そのための北側の大規模な犠牲をも覚悟していた。なにしろプレイクとコンツムに対しては北ベトナム軍は1968年と72年の大攻勢でも激しい攻撃をかけたが、制圧できなかったのだ。
しかし1975年春の両軍のバランスはだいぶ変わっていた。南側にはまずアメリカ軍の直接の支援がまったくなくなった。南軍自体もアメリカからの軍事支援の減少で総合戦力は弱くなった。だがそれでも北側は慎重を期していた。「75年の雨期が到来するまでに」プレイク、コンツムを占拠し、中部高原全体を制圧することを目標としたのだ。ただしその場合でもズン将軍は「わが軍が巧妙かつ敏速に行動すれば」という条件をつけていた。支障が起きる場合も考慮に入れて、「75年から76年の乾期中に中部高原の作戦を終了させる」ということを最終、最遅の目標としていた。この目標はもう少し具体的にいえば、75年12月から76年4月となる。そんな慎重な予定だったのだ。しかしその最終目標の中部高原全体が75年の3月という時点で自壊をみせてきたのだ。ズン将軍が驚き、衝撃を受け、歓喜にまでいたる、という反応を示すのは当然だった。
そのズン将軍自身の反応をズン戦記から伝えよう。
バンメトート西方のジャングルの前線司令部にあったズン将軍は3月15日、米欧側の流した報道にまず首をひねった。西側ラジオ放送局(VOAやBBC)のニュースがバンメトーからサイゴンまでの民間航空機のチケットが通常の10倍に近い4万ピアストル(南べナムの当時の通貨)という闇の高値段に跳ね上がったことを伝えていたのだ。なぜそれほど多くの住民がサイゴンへ向かうのか、という疑問だった。
ズン将軍は翌3月16日夕、配下の参謀たちを集めて、戦況を研究した。この時点ではなお南ベトナム軍の出方を占うことが主題だった。白熱した議論が長く続いた結果、南べトナム軍の出方としては次の3つの可能性が指摘された。
- 南ベトナム軍は中部高原、とくにバンメトート周辺への増援部隊の投入を図り、バンメトートへの反撃と奪回を目指す。
- 南軍は中部高原各地に散った残存部隊をプレイクに集結させ、プレイク防衛に全力をあげる。
- 南軍は中部高原から戦略的撤退をする。
以上の3つの可能性が論じられたが、この時点では(3)の南軍の中部高原全体からの撤退には現実の考慮があまり払われていなかった。そしてこの会議の結論としては北ベトナム軍は当面、中部高原での南ベトナム軍の反撃の殲滅に全力を尽くすことと、プレイクの包囲を急ぐこと、という2点が決められたのだった。
ところがこの決定が下されてすぐの3月16日午後9時すぎ、ズン将軍の前線司令部に重大な報告が届いた。プレイク市内の南ベトナム軍の弾薬庫が爆破され、あちこちで火災が起き、しかも中部高原での南軍戦力の中枢となる機甲部隊までが全軍、撤退を始めた、という報だった。「敵は一体なぜ、こんな退却をするのか」とか「だれがそんな命令を出したのか」という疑問がズン将軍の脳裡を襲った。
ズン将軍がなお半信半疑のまま自問自答した模様をみずから記していた。
「南軍撤退の報告を聞き終わると私の脳裡に過去のフランスやアメリカの軍隊との闘いで敵が敗走する様々な情景がよみがえった。フランス軍との戦いで4号道路を逃げる仏軍ルパージュ将軍の姿、1968年のケサン攻防戦で退却するアメリカ海兵隊、72年にクアンチから退却するサイゴン軍第3師団・・・どの敵もいざ撤退に際しては周到な準備と多様な偽装手段を用いていた。しかしいまや目前の敵は主力軍団がわれ先にと逃走し、戦略的要衝の中部高原全域を放り出している。一体なぜなのか・・・」
ズン将軍は驚きと戸惑いを率直に告白していた。
インドシナの戦争で中隊や大隊が戦闘中に逃走したことはあった。師団規模の敗走や撤退も稀ながらあった。だが複数の師団が集まる軍団が全体として本格的戦闘の前に逃げてしまうという実例は皆無だった。ズン将軍はこの信じがたい事態を事実として確認し、手放しで喜んだ、
「目前の事態を確認して私は限りない歓喜に襲われた。気がはやり、血が騒ぎたてるのを覚えた!」
時をおかず、中部高原の北ベトナム軍各部隊にフルスピードの追撃命令が下された。この稀有の好機を現実の勝利に結びつけるために、撤退する敵を徹底的に叩け、海岸や平野まで逃さず、高原地域で撃滅せよ!
こんな命令が出されたのだった。
(その18につづく。その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11、その12、その13、その14、その15、その16)
トップ写真:ディエンビエンフー北部にパラシュート降下した南ベトナム軍兵士 出典:Hulton Archive/Getty Images
あわせて読みたい
この記事を書いた人
古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授
産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

 執筆記事一覧
執筆記事一覧